目次
職場の同僚や上司など「関わりたくない」と感じる人がいて疲れてしまう人は、少なくありません。さまざまなバックグラウンドを持つ人が集まる職場は、多様な考えや性格の人がいるため、性格が合わない方がいるのはごく自然なことです。
職場は学校などと違い、「関わりたくない人」とも関わらざるを得ない環境でもあります。そのため、精神がすり減って疲れてしまう人も多いでしょう。 そこでこの記事では、職場に関わりたくない人がいる理由から、関わりたくない人の特徴、接し方の工夫などを具体的に解説していきます。
なお、ミイダスのコンピテンシー診断(特性診断)では、どのような上司や部下、同僚と相性が良いか診断が可能です。職場の人間関係にお悩みの方は、ぜひ一度お試しください。
\自分の強みや適性がわかる!/
ミイダスでコンピテンシー診断(特性診断)する

そもそも、なぜ職場に「関わりたくない人」がいるのでしょうか。実は、関わりたくないと感じる相手がいるのは、当然のことだともいえます。ここではその理由をご紹介します。
「自分とは違う」と感じる相手がいることは、集団で働く以上避けられません。そのため「関わりたくない」と感じてしまう相手がいるのは、ごく自然なことだといえます。
仮に意欲的な人材だけの集団だったとしても、時間の経過とともにこの法則が成り立ってしまうとも言われています。 「3・4・3の法則」も似たような法則で、物事に対しての反応や関心が「3割が好意的」「4割が無関心」「3割が非好意的」に分かれるという理論です。
これらの法則から、組織には意欲や関心の度合いがさまざまな人がいるため、全員とうまく付き合うのは非現実的だといえます。
「職場の人なんだから、もっとちゃんとしてほしい」「普通はこうするはず」など、他人に対して無意識に期待をしていないか改めて考えてみましょう。相手が変わらないことにイライラするより、期待値を下げて接したほうが、心が楽になることも少なくありません。
【関連記事:「職場の人間関係に疲れた」と感じてしまう原因やリセット方法を紹介】

職場で「関わりたくない」と感じられてしまう人には、ある程度共通する特徴があります。 ここでは、関わりたくないと感じられる人の特徴を、4つのタイプに分けて紹介します。
あなたが関わりたくないと思っている相手の原因は何かを明確にし、そのあとの対策に役立てましょう。
また、責任を人に押しつけたり、ミスをなかったことにしたりする人も、関わりたくない相手によく見られる特徴です。こうした態度を取っていると、周囲を緊張させやすく、避けられる原因になります。
特に、悪口や人に対する批評が多い人は、「この人には安心して本音を話せない」と思われてしまうでしょう。巻き込まれることを避けたいと考える人が増え、距離を置きたいと思われてしまうのです。
また、相手によって態度を変えるような人も、周囲からの信頼を損ないます。「今日はどんな反応をされるのか」と不安にさせてしまい、周りから自然と距離を取られることもあるでしょう。
また、時間にルーズだったり、清潔感に欠けていたりといった日常的な振る舞いも、周囲から避けられる原因になります。小さな違和感の積み重ねが、徐々に関係性の溝を深めてしまうのです。

関わりたくない相手にストレスを感じると、つい態度や言動に出てしまうことがあります。しかし、一部の行動は状況を悪化させてしまうリスクをはらんでいます。
そこで、ここでは「関わりたくない人」への対応で避けるべきNG行動を4つ紹介します。思い当たる節がある人は、自分の対応を見直すきっかけにしてみてください。
しかし、悪口は本人の耳に入ってしまうことがよくあります。一度関係にヒビが入ると修復は難しく、かえって職場全体の空気が悪くなる原因にもつながるでしょう。
また、「あの人ってさ……」と誰かに同意を求めるような形で話すと、聞いた側にも負担がかかるうえに、集団のような構図ができてしまうこともあります。陰口は一時的な気晴らしにはなるかもしれませんが、職場での信頼を失うリスクがある行動のため、避けるのが無難です。
また、周囲が気まずさを感じてしまい、職場全体の雰囲気を悪くしてしまう原因にもなりかねません。必要最低限の会話すら避けてしまうと、仕事を進めるうえで支障が出る恐れもあります。
さらに、無視や極端な対応は、ハラスメントと受け取られるリスクもあります。たとえ個人的には関わりたくない相手でも、仕事上の一人の同僚であることを意識し、冷静で適切な距離感を保ちつつも、業務に必要なコミュニケーションを取ることが大切です。
言ったほうは一時的にスッキリするかもしれませんが、問題の根本的な解決にはならない可能性が高いです。また、職場の雰囲気も悪くなってしまうかもしれません。 関わりたくない相手ほど、あえて一線を引き、感情的な反応を避けることが自分のためにもなります。
しかし、相手の言動を考え続けることは自分の感情をすり減らし、日々の生活の質を下げてしまいかねません。ときには、知らず知らずのうちに相手と自分を比較して落ち込むこともあるでしょう。
相手のことを延々と考えてしまうのは、ある意味でその人に“心の主導権”を握られてしまっている状態です。意識的に気持ちを切り替え、自分の好きなことや目の前の業務に集中する時間を増やすことが大切です。

関わりたくない人との関係に悩んだときは、まず自分の意識を少し変えてみるのも1つの手です。視点を変えるだけで、心が軽くなることもあります。
ここでは、関わりたくない人との関係で悩んだときの対処法をご紹介します。
仲良くなる必要はないと意識を変えることで、感情的な疲労感が軽減されることもあります。もちろん、完璧に割り切るのは難しいですが、「あの人の態度は気になるけれど、業務には関係ない」のように、意識を切り替える癖を少しずつつけていくと良いでしょう。
また、私生活で何らかの問題があり強いストレスを抱えている人は、職場で感情をうまくコントロールできなくなることもあります。 相手の行動に理由があるのだと考えることで「仕方ないか」と心の中で納得できる余地が生まれ、自分の気持ちを少し楽にすることができるでしょう。
ですが、その期待が裏切られると「やっぱりダメだったか」とがっかりし、余計にストレスを感じてしまいかねません。 最初から過度な期待を持たず、必要以上に相手に期待しないと心がけることで、感情的なダメージを減らせるでしょう。
むしろ、誰とも摩擦が生じず、全員と親しくできる職場のほうが珍しいかもしれません。「苦手な人がいるのは当然」だと受け止めることで、自分を責めたり、無理に関係を改善しようとして疲れたりすることを防げます。
【関連記事:会社で合わない人とうまく付き合うには?職場の人間関係を円滑にするコツ】

ここまで解説したように、職場に関わりたくない相手がいるのは珍しいことではないため、意識を変えることが重要です。
また、関わりづらい人に対する「接し方の工夫」を知っておくことも大切と言えます。ここでは、実践しやすく効果的な方法を5つ紹介します。
そのためには、話す前に「何を伝えるべきか」を簡単に整理しておくことが大切です。あらかじめ話の構成を決めておけば、余計なやり取りに発展しにくくなります。 効率よく、冷静なやり取りを意識することで、感情的なストレスも少しずつ減っていくはずです。
上記のような工夫によって、相手との距離が近くなりすぎるのを防げるでしょう。
社内で偶然2人になる場面を避けることは難しいかもしれませんが、昼休みの席や移動のタイミングをずらすなど、小さな工夫で関わる機会を減らすことは可能です。意識的に1対1になるタイミングを減らしましょう。
上司に相談するのも1つの方法です。自分の状況を理解してもらっているだけで、安心感につながります。 また職場の外でも、信頼できる友人や家族に話すことで、感情の整理がしやすくなります。
無理に1人でなんとかしようとせず、周囲の力を上手に借りることが、心の余裕を生む鍵になります。
たとえば自己分析を経て、自身はコミュニケーションを積極的に行いながら業務を進めたい人だとわかったとします。一方で、相手はなるべく口を挟まずに見守りたいと考えていたら、そもそもの相性が合わないですよね。 このように自分の特性を知ることで、「相性が合わないから仕方ない」「無理に合わせる必要はない」と割り切れるでしょう。
ミイダスのコンピテンシー診断(特性診断)を受検することで、自身の上司や部下としての傾向や苦手な上司や部下、同僚との相性を数値で把握できます。また、パーソナリティの傾向やストレス要因なども分析できるため、自分について客観的に見つめ直すことも可能です。
無料で診断可能ですので、ぜひお試しください。
\自分の強みや適性がわかる!/
ミイダスでコンピテンシー診断(特性診断)する
【関連記事:【嫌いな上司と関わりたくない】上司を嫌う理由10選やうまく付き合うコツを解説 】
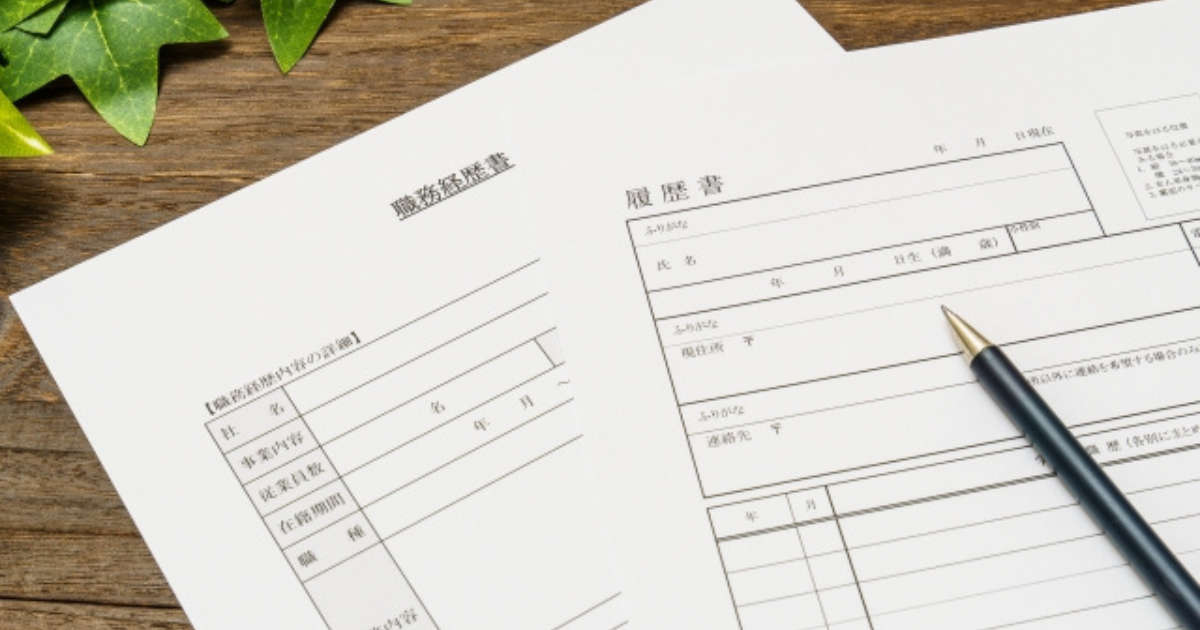
接し方を工夫したり意識転換したりしても、状況が改善しないこともあります。そんなときは自分1人で抱え込まず、会社としての対応を求めたり、環境そのものを見直したりすることも検討してみましょう。
また、チームの再編成や席の配置換え、部署異動などの調整によって、直接の関わりを減らすという選択肢もあるでしょう。職場で長く働く以上、自分だけが我慢を続けるのではなく、組織として問題に向き合ってもらう姿勢も大切です。
人間関係だけでなく、キャリアアップや働き方の見直しといった観点からも、転職には多くの可能性があります。新しい職場では、これまでに感じていた悩みから解放され、前向きな気持ちで働けるかもしれません。

転職を考えている人にとって、同じ業種で転職するのか、異業種で新たな道を進むのかは大きな悩みの1つです。そこでおすすめなのが転職アプリ「ミイダス」です。
自分の能力や特性を把握するのに役立つ「コンピテンシー診断(特性診断)」や、自身の思考の偏り(認知バイアス)を測定できる「バイアス診断ゲーム」を通して、転職の方向性を定めることができます。
ミイダスは企業側が求職者にスカウトをする「スカウト型」の転職サービスです。上記の診断コンテンツを行うと、自分の適性にマッチする求人のスカウトを受けやすくなります。
もちろん、転職を行う意思が固まっていない人は、診断機能を使ってみるだけでも良いでしょう。ぜひミイダスをインストールして、今の仕事を続けるべきか、転職するべきかを考えるきっかけにしてみてください。
\自分の強みや適性がわかる!/
ミイダスでコンピテンシー診断(特性診断)する
職場は学校などと違い、「関わりたくない人」とも関わらざるを得ない環境でもあります。そのため、精神がすり減って疲れてしまう人も多いでしょう。 そこでこの記事では、職場に関わりたくない人がいる理由から、関わりたくない人の特徴、接し方の工夫などを具体的に解説していきます。
なお、ミイダスのコンピテンシー診断(特性診断)では、どのような上司や部下、同僚と相性が良いか診断が可能です。職場の人間関係にお悩みの方は、ぜひ一度お試しください。
ミイダスでコンピテンシー診断(特性診断)する
※登録後に無料で診断できます。
なぜ職場に「関わりたくない人」がいるのか?

そもそも、なぜ職場に「関わりたくない人」がいるのでしょうか。実は、関わりたくないと感じる相手がいるのは、当然のことだともいえます。ここではその理由をご紹介します。
複数人が集まれば、価値観の違いがあるのは当然
職場は、さまざまな価値観や背景を持つ人が集まる場です。年齢や経験、育ってきた環境が違えば、ものの見方や考え方が合わないのは当然のこと。「自分とは違う」と感じる相手がいることは、集団で働く以上避けられません。そのため「関わりたくない」と感じてしまう相手がいるのは、ごく自然なことだといえます。
2・6・2の法則と3・4・3の法則
「2・6・2の法則」と「3・4・3の法則」を聞いたことはありますか?前者は、企業などの組織では人材の比率が「意欲的な2割」「平均的な6割」「意欲が低い2割」に分かれるという法則です。仮に意欲的な人材だけの集団だったとしても、時間の経過とともにこの法則が成り立ってしまうとも言われています。 「3・4・3の法則」も似たような法則で、物事に対しての反応や関心が「3割が好意的」「4割が無関心」「3割が非好意的」に分かれるという理論です。
これらの法則から、組織には意欲や関心の度合いがさまざまな人がいるため、全員とうまく付き合うのは非現実的だといえます。
相手への期待が強すぎる可能性も
相手に対する期待が強すぎると、それに合致しない場合にストレスを感じ「この人とは付き合いたくない」と思ってしまう可能性があります。「職場の人なんだから、もっとちゃんとしてほしい」「普通はこうするはず」など、他人に対して無意識に期待をしていないか改めて考えてみましょう。相手が変わらないことにイライラするより、期待値を下げて接したほうが、心が楽になることも少なくありません。
【関連記事:「職場の人間関係に疲れた」と感じてしまう原因やリセット方法を紹介】
関わりたくない人の特徴

職場で「関わりたくない」と感じられてしまう人には、ある程度共通する特徴があります。 ここでは、関わりたくないと感じられる人の特徴を、4つのタイプに分けて紹介します。
あなたが関わりたくないと思っている相手の原因は何かを明確にし、そのあとの対策に役立てましょう。
攻撃的なタイプ:すぐ否定する人やマウントを取る人
話すたびにマウントを取ってくる人や、ちょっとした意見にもすぐ否定してくる人と一緒に働くのは、ストレスが溜まってしまいます。本人は「正論を言っているだけ」と思っているかもしれませんが、周囲からは「いつもピリピリしてる」「話すと疲れる」と思われていることも少なくありません。また、責任を人に押しつけたり、ミスをなかったことにしたりする人も、関わりたくない相手によく見られる特徴です。こうした態度を取っていると、周囲を緊張させやすく、避けられる原因になります。
ネガティブなタイプ:不満や愚痴、悪口が多い人
職場に愚痴や不満を口にしている人がいると、周囲の空気はどんよりと沈んでしまいます。 本人はただ「話を聞いてほしい」「共感してほしい」と思っているだけかもしれませんが、無意識のうちに周囲にネガティブな感情を抱かれて、嫌われやすいです。特に、悪口や人に対する批評が多い人は、「この人には安心して本音を話せない」と思われてしまうでしょう。巻き込まれることを避けたいと考える人が増え、距離を置きたいと思われてしまうのです。
感情変化が大きいタイプ:機嫌や態度がよく変わる人
機嫌によって態度が変わったり、感情がすぐ表に出たりする人は、周囲の人から関わりたくないと思われやすいです。機嫌の上下が激しい人と接するのは、かなり気を使うため、ストレスの原因となりやすいでしょう。また、相手によって態度を変えるような人も、周囲からの信頼を損ないます。「今日はどんな反応をされるのか」と不安にさせてしまい、周りから自然と距離を取られることもあるでしょう。
自己中心タイプ:時間にルーズな人や不潔な人
自分の都合や価値観を優先する人も、関わりたくないと思われる人の代表的な特徴です。例えば相手の状況を考えずに発言したり、独断で物事を進めたりするような行動は「一緒に仕事したくない」と思われる原因になります。また、時間にルーズだったり、清潔感に欠けていたりといった日常的な振る舞いも、周囲から避けられる原因になります。小さな違和感の積み重ねが、徐々に関係性の溝を深めてしまうのです。
関わりたくない人に対するNG行動

関わりたくない相手にストレスを感じると、つい態度や言動に出てしまうことがあります。しかし、一部の行動は状況を悪化させてしまうリスクをはらんでいます。
そこで、ここでは「関わりたくない人」への対応で避けるべきNG行動を4つ紹介します。思い当たる節がある人は、自分の対応を見直すきっかけにしてみてください。
陰口を言う
関わりたくない相手に対して不満が溜まると、つい陰でその人の悪口を言ってしまうことがあります。誰かに話すことでストレスが少し軽くなるように感じることもあり、「それくらいは仕方ない」と思う人もいるかもしれません。しかし、悪口は本人の耳に入ってしまうことがよくあります。一度関係にヒビが入ると修復は難しく、かえって職場全体の空気が悪くなる原因にもつながるでしょう。
また、「あの人ってさ……」と誰かに同意を求めるような形で話すと、聞いた側にも負担がかかるうえに、集団のような構図ができてしまうこともあります。陰口は一時的な気晴らしにはなるかもしれませんが、職場での信頼を失うリスクがある行動のため、避けるのが無難です。
態度に出す
「相手をあからさまに避ける」「話しかけられたら嫌な顔をする」といった態度は、控えるべきです。このような態度は相手に強い不快感を与え、結果としてあなたへの敵意や反発を生む可能性があります。また、周囲が気まずさを感じてしまい、職場全体の雰囲気を悪くしてしまう原因にもなりかねません。必要最低限の会話すら避けてしまうと、仕事を進めるうえで支障が出る恐れもあります。
さらに、無視や極端な対応は、ハラスメントと受け取られるリスクもあります。たとえ個人的には関わりたくない相手でも、仕事上の一人の同僚であることを意識し、冷静で適切な距離感を保ちつつも、業務に必要なコミュニケーションを取ることが大切です。
論破や皮肉
相手に対して皮肉を交えて批判したり、強い口調で言い返したり、さらには正論で論破したりするのは、良い結果を生みません。たとえ内容が正しくても、相手は「攻撃された」と感じるだけです。言ったほうは一時的にスッキリするかもしれませんが、問題の根本的な解決にはならない可能性が高いです。また、職場の雰囲気も悪くなってしまうかもしれません。 関わりたくない相手ほど、あえて一線を引き、感情的な反応を避けることが自分のためにもなります。
相手のことばかり考える
関わりたくない人のことほど、なぜか頭から離れなくなるものです。気づけば仕事中やプライベートの時間まで、その人のことで頭がいっぱいになっていることもあります。しかし、相手の言動を考え続けることは自分の感情をすり減らし、日々の生活の質を下げてしまいかねません。ときには、知らず知らずのうちに相手と自分を比較して落ち込むこともあるでしょう。
相手のことを延々と考えてしまうのは、ある意味でその人に“心の主導権”を握られてしまっている状態です。意識的に気持ちを切り替え、自分の好きなことや目の前の業務に集中する時間を増やすことが大切です。
関わりたくない人との関係に悩んだときの対処法

関わりたくない人との関係に悩んだときは、まず自分の意識を少し変えてみるのも1つの手です。視点を変えるだけで、心が軽くなることもあります。
ここでは、関わりたくない人との関係で悩んだときの対処法をご紹介します。
仕事だと割り切る
関わりたくない人と接することが避けられない場面では、「これは仕事だから仕方ない」と意識的に割り切ることが、有効な対処法の1つです。仕事である以上、多少の相性の悪さや考え方の違いがあっても、必要最低限のやり取りさえできていれば、業務上の支障はありません。仲良くなる必要はないと意識を変えることで、感情的な疲労感が軽減されることもあります。もちろん、完璧に割り切るのは難しいですが、「あの人の態度は気になるけれど、業務には関係ない」のように、意識を切り替える癖を少しずつつけていくと良いでしょう。
相手の事情を推察する
「どうしてあの人はあんな態度なんだろう」と感じたとき、その裏にある“事情”を想像してみましょう。 たとえば、育ってきた環境が違えば、価値観や言葉の選び方にズレがあるのも当然です。また、私生活で何らかの問題があり強いストレスを抱えている人は、職場で感情をうまくコントロールできなくなることもあります。 相手の行動に理由があるのだと考えることで「仕方ないか」と心の中で納得できる余地が生まれ、自分の気持ちを少し楽にすることができるでしょう。
相手に期待しない
職場で関わりたくない人に対しても、「今度こそはちゃんとやってくれるかも」「前に注意したから、少しは改善しているはず」と、つい期待してしまうことがあります。ですが、その期待が裏切られると「やっぱりダメだったか」とがっかりし、余計にストレスを感じてしまいかねません。 最初から過度な期待を持たず、必要以上に相手に期待しないと心がけることで、感情的なダメージを減らせるでしょう。
苦手な人がいるのは当然
冒頭でもお伝えしたように、職場には多様な価値観や性格を持つ人たちが集まっています。全員と気が合うことは珍しく、苦手だと感じる相手がいるのは自然なことです。むしろ、誰とも摩擦が生じず、全員と親しくできる職場のほうが珍しいかもしれません。「苦手な人がいるのは当然」だと受け止めることで、自分を責めたり、無理に関係を改善しようとして疲れたりすることを防げます。
【関連記事:会社で合わない人とうまく付き合うには?職場の人間関係を円滑にするコツ】
関わりたくない人とうまく接する方法

ここまで解説したように、職場に関わりたくない相手がいるのは珍しいことではないため、意識を変えることが重要です。
また、関わりづらい人に対する「接し方の工夫」を知っておくことも大切と言えます。ここでは、実践しやすく効果的な方法を5つ紹介します。
話は簡潔に、結論から伝える
関わりたくない相手との会話は、なるべく短時間で済ませましょう。そのため、結論から先に伝えるのがおすすめです。要点を端的に伝えることで、必要以上に会話が長引くのを防げます。そのためには、話す前に「何を伝えるべきか」を簡単に整理しておくことが大切です。あらかじめ話の構成を決めておけば、余計なやり取りに発展しにくくなります。 効率よく、冷静なやり取りを意識することで、感情的なストレスも少しずつ減っていくはずです。
自分は忙しい人だと思わせる
関わりたくない人に対して壁をつくっていることがバレると、かえって関係がこじれてしまうことがあります。そこで有効なのが、「忙しい人」という印象を周囲に持たせることです。 常に何かに取り組んでいるように振る舞えば、相手から話しかけられる機会が減ります。- 席を立つときにメモ帳を持って歩く
- デスクに書類を広げておく
- パソコンに向かいながら軽く会釈だけする
上記のような工夫によって、相手との距離が近くなりすぎるのを防げるでしょう。
2人きりにならないように工夫する
関わりたくない人と接さなくてはならないときは、2人きりにならないように意識するのも1つの工夫です。誰かを巻き込んで複数人でのやりとりに切り替えることで、負担を軽減できます。社内で偶然2人になる場面を避けることは難しいかもしれませんが、昼休みの席や移動のタイミングをずらすなど、小さな工夫で関わる機会を減らすことは可能です。意識的に1対1になるタイミングを減らしましょう。
第三者の力を借りる
関わりたくない人との関係に悩んだとき、1人で抱え込まないことも大切です。 たとえば、業務中のやり取りが負担になっている場合は、同僚に同席してもらったり、グループでの作業に切り替えるよう調整してもらったりと、さりげなく第三者を巻き込んでみましょう。上司に相談するのも1つの方法です。自分の状況を理解してもらっているだけで、安心感につながります。 また職場の外でも、信頼できる友人や家族に話すことで、感情の整理がしやすくなります。
無理に1人でなんとかしようとせず、周囲の力を上手に借りることが、心の余裕を生む鍵になります。
自己分析を行う
客観的な数値をもとに自己分析を行うと、視野が広がるでしょう。関わりたくない人と対峙した際に「関係を良くしないと……」と考えがちですが、そもそも相性が合わないだけかもしれません。たとえば自己分析を経て、自身はコミュニケーションを積極的に行いながら業務を進めたい人だとわかったとします。一方で、相手はなるべく口を挟まずに見守りたいと考えていたら、そもそもの相性が合わないですよね。 このように自分の特性を知ることで、「相性が合わないから仕方ない」「無理に合わせる必要はない」と割り切れるでしょう。
ミイダスのコンピテンシー診断(特性診断)を受検することで、自身の上司や部下としての傾向や苦手な上司や部下、同僚との相性を数値で把握できます。また、パーソナリティの傾向やストレス要因なども分析できるため、自分について客観的に見つめ直すことも可能です。
無料で診断可能ですので、ぜひお試しください。
ミイダスでコンピテンシー診断(特性診断)する
※登録後に無料で診断できます。
【関連記事:【嫌いな上司と関わりたくない】上司を嫌う理由10選やうまく付き合うコツを解説 】
それでも解決できない場合の最終手段
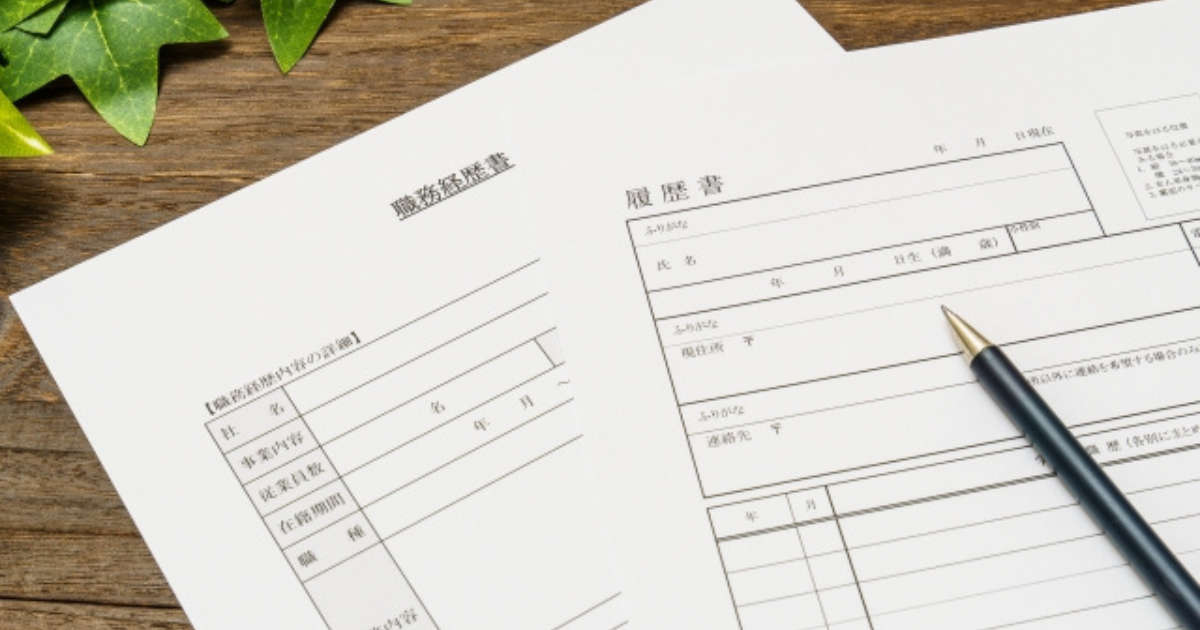
接し方を工夫したり意識転換したりしても、状況が改善しないこともあります。そんなときは自分1人で抱え込まず、会社としての対応を求めたり、環境そのものを見直したりすることも検討してみましょう。
会社として対応してもらう
個人の努力や工夫だけではどうにもならない場合は、会社に対応を求めることも必要です。たとえば、上司に相談して状況を説明し、本人への注意や指導をしてもらうことで、相手の態度が変わる可能性があります。また、チームの再編成や席の配置換え、部署異動などの調整によって、直接の関わりを減らすという選択肢もあるでしょう。職場で長く働く以上、自分だけが我慢を続けるのではなく、組織として問題に向き合ってもらう姿勢も大切です。
転職を検討する
あらゆる対処を講じても状況が変わらない場合や、職場そのものに問題があると感じる場合は、転職を視野に入れるのも1つの選択肢です。「逃げ」ではなく、自分を守るための前向きな判断として、新しい環境に踏み出すのも大切と言えます。人間関係だけでなく、キャリアアップや働き方の見直しといった観点からも、転職には多くの可能性があります。新しい職場では、これまでに感じていた悩みから解放され、前向きな気持ちで働けるかもしれません。
転職を考えているならミイダス

転職を考えている人にとって、同じ業種で転職するのか、異業種で新たな道を進むのかは大きな悩みの1つです。そこでおすすめなのが転職アプリ「ミイダス」です。
自分の能力や特性を把握するのに役立つ「コンピテンシー診断(特性診断)」や、自身の思考の偏り(認知バイアス)を測定できる「バイアス診断ゲーム」を通して、転職の方向性を定めることができます。
ミイダスは企業側が求職者にスカウトをする「スカウト型」の転職サービスです。上記の診断コンテンツを行うと、自分の適性にマッチする求人のスカウトを受けやすくなります。
もちろん、転職を行う意思が固まっていない人は、診断機能を使ってみるだけでも良いでしょう。ぜひミイダスをインストールして、今の仕事を続けるべきか、転職するべきかを考えるきっかけにしてみてください。
ミイダスでコンピテンシー診断(特性診断)する
※登録後に無料で診断できます。


