「ついスマホを触ってしまう」「やるべきことがあるのに手がつかない」そんなサボり癖に悩む社会人は少なくありません。 働き方の多様化により、社会人になってもサボる習慣が抜けない、あるいは職場の環境が原因でサボってしまうケースも増えています。
また、サボり癖のある同僚や部下にどう対応すべきか悩んでいる人もいるでしょう。 本記事では、社会人にサボり癖がつく原因やサボり癖がもたらす悪影響、改善方法について解説します。さらに、周囲にサボり癖のある人がいる場合の対処法や、環境が合わない場合の転職という選択肢についても紹介します。

サボり癖と聞くと「本人の甘え」と捉えられがちですが、その背景にはさまざまな要因が絡んでいます。学生の頃からの習慣や性格的な特性に加え、働く環境や職場の制度も大きく影響します。
社会人にサボり癖がつく原因について、個人と環境の両面から見てみましょう。
学生の頃は「キャラ」としてサボる性格が周りの友人たちに受け入れられたり、大きな問題に発展しなかったりすることも多く、気づかぬうちにそれが自分のスタイルになっていることもあります。 しかし社会人になると、そうした行動が評価や信頼に直結するようになります。
さらに、集団で仕事をする際にはこの現象が顕著に現れます。これは「リンゲルマン効果」と呼ばれる、人数が増えるほど1人あたりの努力量が低下するという現象でも説明できます。サボり癖は特別なことではなく、誰にでも起こり得ることといえるでしょう。
また目標を設定していたとしても、その目標が高すぎると、自分には無理だと感じて手が止まってしまうケースもあります。自分に合ったレベル感で目標を設定しないと、サボり癖がつきやすいでしょう。
また、業務内容や職場の価値観が自分と合っていない状況も、サボり癖の原因となります。仕事に前向きに取り組みにくくなり、モチベーションが下がってサボる行動につながるのです。
本人の努力不足や意志の弱さと片付けられがちですが、こうした特性がある人にとっては「やろうとしても行動に移せない」ことが多いです。原因を正しく理解することで、適切な対処方法が見えてくることもあります。
また在宅勤務の場合、人の目がないため緊張感が薄れやすく、サボり癖が出やすい環境と言えます。仕事とプライベートの切り替えがうまくできないと、集中力が続かず、つい誘惑に流される場面も増えてしまうでしょう。
このように感じれば、真面目に取り組む意欲は薄れ、サボりたい気持ちが湧いてきます。また、仕事内容や自身の活躍に対して給与が低いと感じることも、サボり癖を助長する大きな要因の1つです。
自分の意志が反映されにくい環境は、仕事に意味を見いだせなくなります。その結果、仕事をサボりたくなってしまうのです。
【関連記事:「仕事に行きたくない⋯」仕事で憂鬱になる原因とは?対処法や転職の注意点を解説】
【関連記事:「仕事を頑張れない…」のは甘え?頑張れなくなる理由7つや解決策を徹底解説】

サボり癖はその場しのぎにはなっても、長い目で見ると自分にとってリスクが多くあります。ここでは、社会人がサボり癖を放置した場合に生じるデメリットを解説します。
その結果、任せてもらえる仕事の幅が狭まったり、大事な場面で声がかからなくなったりすることも考えられます。
こうした状況は組織全体の士気を下げ、生産性の低下や人間関係の悪化につながる恐れもあります。
表面的には楽をしていても、内面ではモヤモヤした感情を抱えている人は意外と多いようです。このような心理状態が続くと、仕事に対する前向きな気持ちも失われ、負のスパイラルに落ち入ってしまいます。
手を抜いてしまうとスキルや知識が蓄積されず、いつまでも次のステップに進めなくなってしまいます。 また、積極的に取り組んでいる人と比べて、評価や成長スピードに差がつくこともあるでしょう。将来的なキャリアに影響する可能性も大きいと言えます。
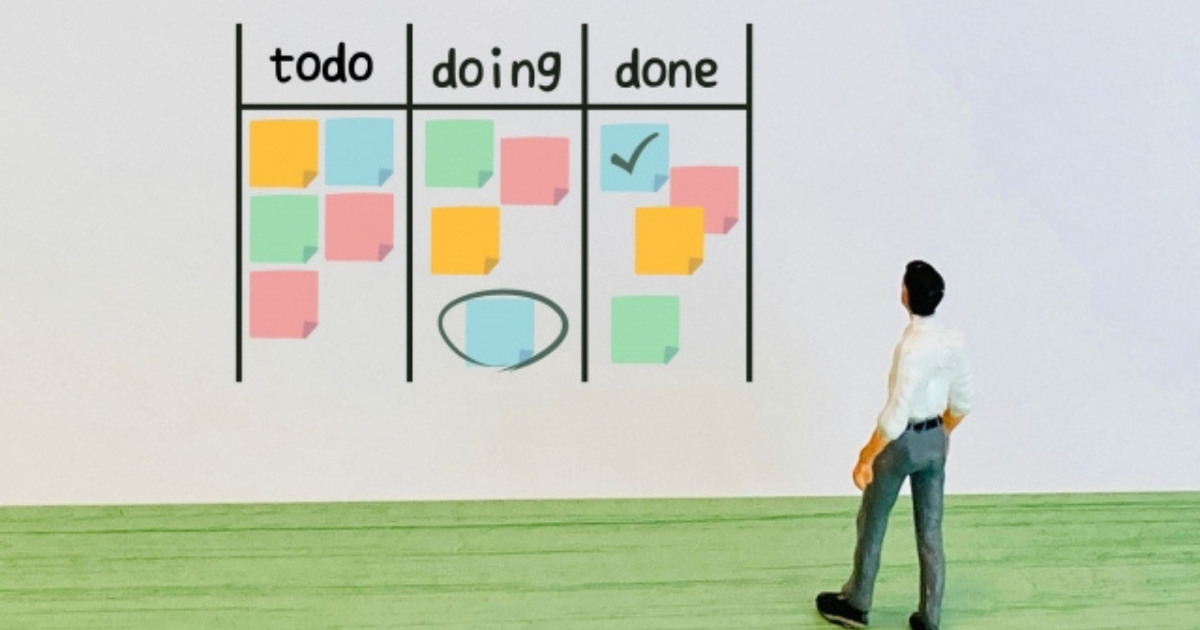
サボり癖を放置しておくとさまざまな悪影響があります。ここでは、具体的で実践しやすい7つのサボり癖の直し方を紹介します。
大きな仕事を細かく分けて書き出すことで、取りかかるハードルが下げられます。 一方で、やらないことリストも効果的です。たとえば「仕事中にSNSを見ない」や「30分以上スマホをいじらない」など、しない行動を明確にすることで集中力を保ちやすくなります。
大切なのは「まずやってみる」という姿勢です。最初から完璧を目指さず、できることから着手することがサボり癖の解消につながります。
特に、「なりたくない自分」を明確にすると反面教師としての効果が得られます。理想の自分に近づくためには、サボってはいけないと気づけるはずです。
【関連記事:仕事で「やりたいことがない」と悩む人はミイダスの可能性診断を活用しよう】
仕事を「自分のための行動」ととらえることで、前向きに取り組めるようになるでしょう。
【関連記事:仕事のやる気が出ない!主な原因と仕事の目的意識をあげる方法】
また、自宅よりカフェやコワーキングスペースのほうがはかどる人もいるでしょう。自分の集中のパターンを把握し、それに合わせて仕事の予定を組み立てることが大切です。
無理に苦手な時間に詰め込もうとすると、かえって集中力が落ち、サボり癖を助長しかねません。自分にとって効率のよいタイミングと環境を見つけてみましょう。
「今日はなぜ手が止まったのか」「どの時間帯に集中できたのか」などを記録してみましょう。 またポジティブな出来事も書いておくと、自分のことを評価してあげられます。
「ちゃんと取り組めた」「予定通り終えられた」と感じることが、次の行動へのモチベーションにもつながるのです。
あらかじめ「この時間は思い切って休む」と決めておくと、心にも余裕が生まれるでしょう。休むことに罪悪感を抱かず、意識的にリフレッシュの時間を確保することで、次の行動にしっかりと力を注げるはずです。

ここまで、サボり癖があることに困っている人自身に向けた直し方を紹介してきました。一方で、サボり癖がある部下や同僚に悩まされている人も少なくないでしょう。
そこで、サボり癖が見られる相手にどう向き合えばいいのか、状況に応じた4つのアプローチを紹介します。
たとえば、最近の働きぶりについて話す機会を設けたり、具体的なサボり行動を指摘したりすることで、自分の状態を客観視してもらえます。責めるのではなく相手の意見を聞く姿勢を持つことで、本人も心を開きやすくなり、意識の改善につながるでしょう。
また、本人の得意分野や関心のある分野を踏まえ、業務を割り振るのも1つの方法です。「やらされている」という感覚が減って主体性が生まれ、行動にも変化が現れやすくなります。
不公平感にイライラしてしまうときは、「そのぶん自分は成長している」という意識に切り替えてみましょう。 「同じ給料をもらっているのに、あの人だけずるい……」と思ってしまうかもしれませんが、感情を落ち着かせて冷静に線を引くことで、必要以上にストレスを抱えずに済みます。
「最近少し様子が違う」と感じた時点で声をかけることで、軌道修正しやすくなります。いきなり厳しく指摘するのではなく、初めは「何か変わったことがあったのか」などとソフトに尋ねると良いでしょう。
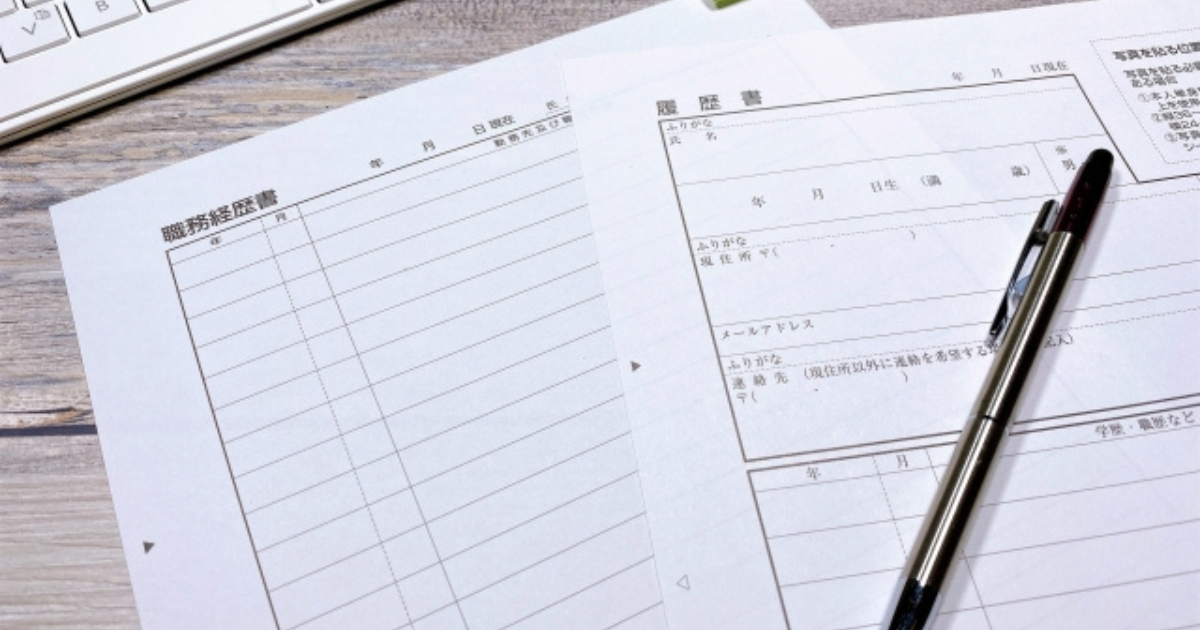
サボり癖にはさまざまな要因が考えられますが、職場環境そのものが原因にあることもあります。環境の改善が見込めないのであれば、環境を変えるという選択肢も視野に入れるべきです。
職場の人間関係や評価制度など、自分で努力しても変えられない環境は存在します。そうしたなかで無理に続けるより、自分に合った場所に身を置いたほうが、本来の力を発揮でき、サボり癖も改善される可能性があるでしょう。
大切なのは、今の職場で頑張り続けることが正解かどうかを、一度立ち止まって考えることです。転職は、よりよい働き方を模索するための前向きな手段と言えます。
このような失敗を避けるために、ミイダスが提供している「可能性診断」が役に立ちます。 ミイダスの「可能性診断」を活用すれば、自分がどのような求人にマッチしそうなのか客観的にわかります。
自分に合った会社に転職したいなら、転職アプリ「ミイダス」をお試しください。登録や診断はすべて無料です。
\自分の強みや適性がわかる!/
ミイダスでコンピテンシー診断(特性診断)する
また、サボり癖のある同僚や部下にどう対応すべきか悩んでいる人もいるでしょう。 本記事では、社会人にサボり癖がつく原因やサボり癖がもたらす悪影響、改善方法について解説します。さらに、周囲にサボり癖のある人がいる場合の対処法や、環境が合わない場合の転職という選択肢についても紹介します。
「転職を考えているけれど、仕事選びで失敗したくない」
「自分の強みや向いている仕事を知りたい」
そんな方は、ミイダスの「コンピテンシー診断(特性診断)」を受けて自分に合った仕事を見つけましょう。
関連記事:転職できる?可能性診断ならミイダスの「コンピテンシー診断(特性診断)」
\自分の強みや適性がわかる!/ ミイダスでコンピテンシー診断(特性診断)する
「自分の強みや向いている仕事を知りたい」
そんな方は、ミイダスの「コンピテンシー診断(特性診断)」を受けて自分に合った仕事を見つけましょう。
関連記事:転職できる?可能性診断ならミイダスの「コンピテンシー診断(特性診断)」
※登録後に無料で診断できます。
社会人のサボり癖の原因

サボり癖と聞くと「本人の甘え」と捉えられがちですが、その背景にはさまざまな要因が絡んでいます。学生の頃からの習慣や性格的な特性に加え、働く環境や職場の制度も大きく影響します。
社会人にサボり癖がつく原因について、個人と環境の両面から見てみましょう。
学生時代についた癖が抜けない
学生時代に「ギリギリまで手をつけない」「最低限のことだけやって乗り切る」といった習慣が身につくと、社会人になって急にその癖をなくすのは簡単ではありません。学生の頃は「キャラ」としてサボる性格が周りの友人たちに受け入れられたり、大きな問題に発展しなかったりすることも多く、気づかぬうちにそれが自分のスタイルになっていることもあります。 しかし社会人になると、そうした行動が評価や信頼に直結するようになります。
人は楽をしたがる生き物
人は本来、できるだけ労力をかけずに成果を得ようとする生き物です。これは生物としての生存本能や省エネ思考に根ざした自然な傾向といえます。たとえ真面目な人でも、意識しなければ無意識のうちに「少しぐらいなら…」とサボる方向に傾いてしまうこともあるでしょう。さらに、集団で仕事をする際にはこの現象が顕著に現れます。これは「リンゲルマン効果」と呼ばれる、人数が増えるほど1人あたりの努力量が低下するという現象でも説明できます。サボり癖は特別なことではなく、誰にでも起こり得ることといえるでしょう。
目標設定ができていない
目標設定が苦手だと、仕事に集中しづらくなり、結果としてサボり癖がつきやすくなります。ゴールが不明確だと何に力を入れればよいかわからず、やる気を失いやすいです。また目標を設定していたとしても、その目標が高すぎると、自分には無理だと感じて手が止まってしまうケースもあります。自分に合ったレベル感で目標を設定しないと、サボり癖がつきやすいでしょう。
仕事に関心・やりがいがない
そもそも今の仕事に関心ややりがいを感じられないと、サボり癖が出やすくなります。目的や意味を見いだせない作業を続けていると、意欲が湧かず、集中力も続きにくくなるためです。また、業務内容や職場の価値観が自分と合っていない状況も、サボり癖の原因となります。仕事に前向きに取り組みにくくなり、モチベーションが下がってサボる行動につながるのです。
心が疲れている
心が疲れていると、仕事に集中したくても気力が湧かず、ついサボってしまうことがあります。精神的な疲れに自分でも気づかないうちに影響を受けているかもしれません。 なお、心の疲れの原因は必ずしも仕事とは限りません。家庭や人間関係などプライベートでのストレスが影響している場合もあります。先天的な原因の可能性も
サボり癖には、発達特性や先天的な要因が関係している場合もあります。たとえば、ADHDの傾向があると集中力が続きにくかったり、計画的に行動することが苦手だったりするため、サボっているように見えることがあるでしょう。本人の努力不足や意志の弱さと片付けられがちですが、こうした特性がある人にとっては「やろうとしても行動に移せない」ことが多いです。原因を正しく理解することで、適切な対処方法が見えてくることもあります。
組織や環境にサボりたくなる雰囲気がある
職場の雰囲気や働く環境が、気がゆるむ原因になることがあります。周囲がダラダラしていると自分もサボりたくなりますし、成果よりも“頑張っている感”が求められるような職場だと、やる気を保つのは難しいです。また在宅勤務の場合、人の目がないため緊張感が薄れやすく、サボり癖が出やすい環境と言えます。仕事とプライベートの切り替えがうまくできないと、集中力が続かず、つい誘惑に流される場面も増えてしまうでしょう。
報酬や評価制度が曖昧・不公平
「自分の頑張りが正しく評価されていない」と感じると、やる気は自然と下がっていきます。- 成果を出しても報酬や昇進に結びつかない
- 評価の基準が不明確
- 一部の人だけが優遇されている
このように感じれば、真面目に取り組む意欲は薄れ、サボりたい気持ちが湧いてきます。また、仕事内容や自身の活躍に対して給与が低いと感じることも、サボり癖を助長する大きな要因の1つです。
意思決定の裁量が少ない
仕事で自身の裁量が少ないと「やらされている」と感じて、やる気を失いやすくなります。上司の指示通りに動くだけ、細かな手順まで管理されているといった状況では、自分の判断で仕事を進める余地がなく、受け身の姿勢になってしまいやすいです。自分の意志が反映されにくい環境は、仕事に意味を見いだせなくなります。その結果、仕事をサボりたくなってしまうのです。
【関連記事:「仕事に行きたくない⋯」仕事で憂鬱になる原因とは?対処法や転職の注意点を解説】
【関連記事:「仕事を頑張れない…」のは甘え?頑張れなくなる理由7つや解決策を徹底解説】
サボり癖のデメリット

サボり癖はその場しのぎにはなっても、長い目で見ると自分にとってリスクが多くあります。ここでは、社会人がサボり癖を放置した場合に生じるデメリットを解説します。
周囲の信用がなくなる
仕事をサボっている姿は、周囲から見られています。周りから「サボり癖がある人」だという印象を持たれると、信用を失いやすいです。その結果、任せてもらえる仕事の幅が狭まったり、大事な場面で声がかからなくなったりすることも考えられます。
他者のモチベーションを下げる
サボり癖は本人だけでなく、その様子を見ている周囲にも悪影響を与えます。特にチームで働く場面では「あの人が手を抜いているのに、なぜ自分だけ頑張らなければならないのか」と不公平感を抱かせてしまうでしょう。こうした状況は組織全体の士気を下げ、生産性の低下や人間関係の悪化につながる恐れもあります。
自信喪失や自己嫌悪で気持ちが落ち込む
サボってしまったことに対して、あとから自己嫌悪を感じる人は少なくありません。「自分はダメだ」という反省が積み重なると、徐々に自信を失っていくでしょう。表面的には楽をしていても、内面ではモヤモヤした感情を抱えている人は意外と多いようです。このような心理状態が続くと、仕事に対する前向きな気持ちも失われ、負のスパイラルに落ち入ってしまいます。
成長の機会を失う
サボることが習慣になると、本来得られるはずだった経験や学びのチャンスを逃してしまいます。仕事を通した成長は、日々の小さな積み重ねによって得られるものです。手を抜いてしまうとスキルや知識が蓄積されず、いつまでも次のステップに進めなくなってしまいます。 また、積極的に取り組んでいる人と比べて、評価や成長スピードに差がつくこともあるでしょう。将来的なキャリアに影響する可能性も大きいと言えます。
サボり癖の直し方
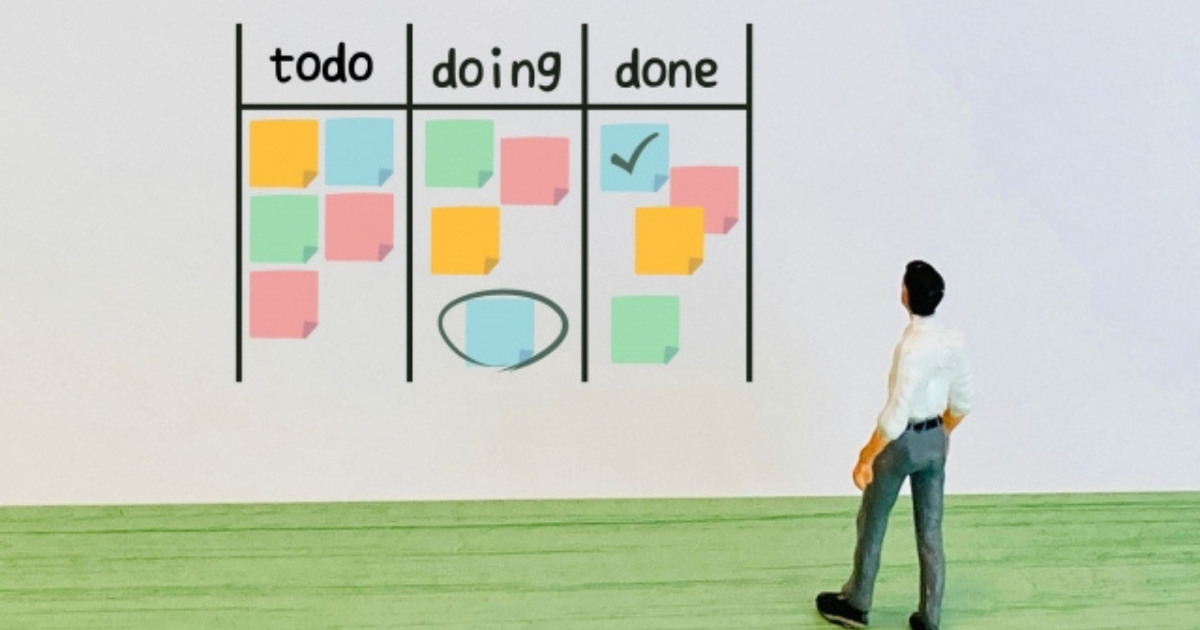
サボり癖を放置しておくとさまざまな悪影響があります。ここでは、具体的で実践しやすい7つのサボり癖の直し方を紹介します。
やることリスト・やらないことリストを作る
やるべきことが頭の中で散らかったままだと、優先順位がつけられず、後回しにしがちです。まずは、やることリストを作ってタスクを可視化しましょう。大きな仕事を細かく分けて書き出すことで、取りかかるハードルが下げられます。 一方で、やらないことリストも効果的です。たとえば「仕事中にSNSを見ない」や「30分以上スマホをいじらない」など、しない行動を明確にすることで集中力を保ちやすくなります。
完璧主義をやめる
「完璧にやらなければ意味がない」という考えにとらわれると、行動そのものが面倒になり、サボってしまう原因になります。理想を高く持つのは良いことですが、過度な完璧主義は、行動のブレーキになってしまいやすいです。大切なのは「まずやってみる」という姿勢です。最初から完璧を目指さず、できることから着手することがサボり癖の解消につながります。
理想の自分・なりたくない自分を思い描く
サボってしまいそうなときは、「自分がどうなりたいのか」「どうなりたくないのか」を思い描いてみるのも有効な方法です。「やる気がない人と思われたくない」「将来的にはもっと責任ある仕事をしたい」など、具体的なイメージを持つことで、自分の行動をコントロールしやすくなるでしょう。特に、「なりたくない自分」を明確にすると反面教師としての効果が得られます。理想の自分に近づくためには、サボってはいけないと気づけるはずです。
【関連記事:仕事で「やりたいことがない」と悩む人はミイダスの可能性診断を活用しよう】
ご褒美を用意する
自分へのご褒美を用意してみるのも1つの方法です。「この作業が終わったらスイーツを食べる」「1週間頑張ったら欲しかったものを買う」などの小さな楽しみがあるだけで、行動へのハードルはぐっと下がります。仕事を「自分のための行動」ととらえることで、前向きに取り組めるようになるでしょう。
【関連記事:仕事のやる気が出ない!主な原因と仕事の目的意識をあげる方法】
集中できる時間帯・場所を見つける
人によって集中できる時間帯や場所は異なります。朝型の人もいれば、夕方以降に調子が出る人もいます。また、自宅よりカフェやコワーキングスペースのほうがはかどる人もいるでしょう。自分の集中のパターンを把握し、それに合わせて仕事の予定を組み立てることが大切です。
無理に苦手な時間に詰め込もうとすると、かえって集中力が落ち、サボり癖を助長しかねません。自分にとって効率のよいタイミングと環境を見つけてみましょう。
1日の行動を日記やメモで振り返る
サボり癖を直すには、自分の行動を客観的に見つめることも重要です。そのためには、1日の終わりに簡単な日記やメモをつけて振り返る習慣をつけるのが効果的です。「今日はなぜ手が止まったのか」「どの時間帯に集中できたのか」などを記録してみましょう。 またポジティブな出来事も書いておくと、自分のことを評価してあげられます。
「ちゃんと取り組めた」「予定通り終えられた」と感じることが、次の行動へのモチベーションにもつながるのです。
メリハリをつけて休む
サボり癖を直すためには「しっかり働き、しっかり休む」というメリハリのあるリズムが不可欠です。ダラダラと中途半端に働く状態が続くと、かえって疲れが溜まり、やる気も失われてしまいます。あらかじめ「この時間は思い切って休む」と決めておくと、心にも余裕が生まれるでしょう。休むことに罪悪感を抱かず、意識的にリフレッシュの時間を確保することで、次の行動にしっかりと力を注げるはずです。
サボり癖がある部下や同僚への対処方法

ここまで、サボり癖があることに困っている人自身に向けた直し方を紹介してきました。一方で、サボり癖がある部下や同僚に悩まされている人も少なくないでしょう。
そこで、サボり癖が見られる相手にどう向き合えばいいのか、状況に応じた4つのアプローチを紹介します。
サボり癖を自覚させる
サボり癖がある人の中には、自覚がない人や、「このくらいは許容範囲だろう」と考えている人もいます。悪意があるわけではなく、単に行動が習慣化してしまっているケースも多いため、まずは気づきを促すことが大切です。たとえば、最近の働きぶりについて話す機会を設けたり、具体的なサボり行動を指摘したりすることで、自分の状態を客観視してもらえます。責めるのではなく相手の意見を聞く姿勢を持つことで、本人も心を開きやすくなり、意識の改善につながるでしょう。
やりがいを与える
サボり癖の背景には、仕事に対する意義ややりがいを見出せていないことがあります。そのような場合は、ただ注意するよりも「この仕事にはどういう意味があるのか」「あなたの存在がどうプラスになるか」を伝えるほうが効果的です。また、本人の得意分野や関心のある分野を踏まえ、業務を割り振るのも1つの方法です。「やらされている」という感覚が減って主体性が生まれ、行動にも変化が現れやすくなります。
自分は自分と割り切る
どれだけ配慮しても相手が変わらないこともあります。そうした場合は「自分の仕事に集中する」というスタンスを持つことも大切です。 常に他人のサボり癖を気にしていては、自分のパフォーマンスまで落ちてしまいます。不公平感にイライラしてしまうときは、「そのぶん自分は成長している」という意識に切り替えてみましょう。 「同じ給料をもらっているのに、あの人だけずるい……」と思ってしまうかもしれませんが、感情を落ち着かせて冷静に線を引くことで、必要以上にストレスを抱えずに済みます。
小さな乱れを見逃さずに対処する
サボり癖は、最初は小さな遅刻や納期のズレなどから始まり、それを放置すると徐々に習慣化していくことがあります。だからこそ、上司などは最初の“乱れ”を見逃さないことが重要です。「最近少し様子が違う」と感じた時点で声をかけることで、軌道修正しやすくなります。いきなり厳しく指摘するのではなく、初めは「何か変わったことがあったのか」などとソフトに尋ねると良いでしょう。
環境に原因がある場合は転職という方法も
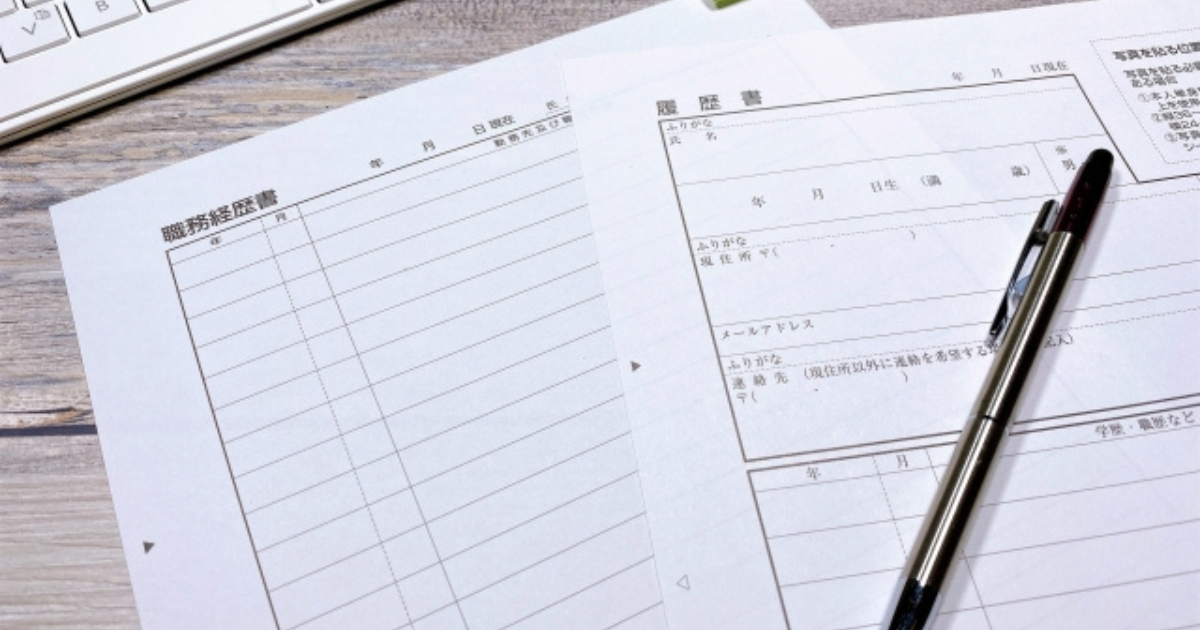
サボり癖にはさまざまな要因が考えられますが、職場環境そのものが原因にあることもあります。環境の改善が見込めないのであれば、環境を変えるという選択肢も視野に入れるべきです。
「逃げるは恥」ではなく「戦略」
「転職は逃げだ」と思っていませんか?たしかに、キャリアアップなど前向きな理由以外の転職は「逃げ」と捉えられることもあります。ですが、その逃げは「戦略」とも言えます。職場の人間関係や評価制度など、自分で努力しても変えられない環境は存在します。そうしたなかで無理に続けるより、自分に合った場所に身を置いたほうが、本来の力を発揮でき、サボり癖も改善される可能性があるでしょう。
大切なのは、今の職場で頑張り続けることが正解かどうかを、一度立ち止まって考えることです。転職は、よりよい働き方を模索するための前向きな手段と言えます。
転職なら「ミイダス」
転職を視野に入れ始めた人は、何から手を付ければいいのか迷いがちです。そんな方におすすめなのが、転職アプリ「ミイダス」です。 転職しても、仕事内容や社風がマッチしなければ思うように活躍できず、再びサボり癖が出てきてしまう可能性もあります。このような失敗を避けるために、ミイダスが提供している「可能性診断」が役に立ちます。 ミイダスの「可能性診断」を活用すれば、自分がどのような求人にマッチしそうなのか客観的にわかります。
自分に合った会社に転職したいなら、転職アプリ「ミイダス」をお試しください。登録や診断はすべて無料です。
ミイダスでコンピテンシー診断(特性診断)する
※登録後に無料で診断できます。


