目次
「自己PRで傾聴力があることを効果的にアピールしたい」
「面接で差別化できるアピール方法を知りたい」
このように考えている方もいるのではないでしょうか。傾聴力は相手の話を聞いて、本音を引き出せるスキルのことを指します。
傾聴力は仕事での人間関係やスムーズな業務に役立つため、自己PRでアピールしたいと考えている方も多いです。しかし、アピールポイントになるぶん他の転職希望者と被りやすいスキルでもあるため、差別化して効果的に伝えるのが転職成功のカギになります。
この記事では、傾聴力がある人の特徴やうまくアピールするコツ、職種別の傾聴力があることを伝えられる自己PR例文7選を紹介します。転職時の自己PRで傾聴力をアピールしたい方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。

自己PRで活用できる傾聴力とは「相手の話をしっかり聞いて、相手が伝えたい話を引き出せるスキル」のことです。 傾聴力と聞くと「静かに話を聞く力」を指すことが多いです。
しかし、それだけでは受け身の印象を与えやすく、転職活動での効果的なアピールにはつながりづらいでしょう。 相手が気持ちよく話せるように適切なタイミングで相槌を打ったり、より掘り下げた質問ができたりと相手の話を引き出せる傾聴力があると、ビジネスにおいて信頼を築くのに役立ちます。
【関連記事:【長所別】面接で使える自己PRの例文5選|強みの見つけ方も紹介】

以下では傾聴力がある人の特徴を4つ紹介します。
「自分は本当に傾聴力があるのだろうか」と考えている人は、当てはまっていないか確認してみてください。
その場の空気や相手のちょっとした仕草や表情を察知して、言葉にしていない感情を感じ取れるのも特徴です。
「自分も同じような経験があるから苦労がわかる」「これを伝えたら喜ぶだろうな」など、相手の感情を肯定できるため、話す側も安心して本心や悩みを語れて信頼関係につながりやすいです。
同じ相槌ばかりではなく、上記のように話の内容によって適切な相槌を使い分けられると、相手は話を聞いてくれていると安心でき、会話も盛り上がるでしょう。
また、調べてわかるような質問をするのではなく、相手の話を掘り下げたり意見を尋ねたりする質問ができると、話している本人も気づいていなかった本音を引き出せるでしょう。 その結果、「この人とは話しやすい」「いろいろな気づきを得られて面白い」と思われやすくなります。
そのため、相手も話を聞いてもらうことで思考が整理されたり、具体的な解決策を見つけられたりするでしょう。このように傾聴力がある人は「安心して相談できる人」と認識してもらいやすく、周囲から頼りにされる存在になることが多いです。

ビジネスにおいて傾聴力が重視されるのには、どのような理由があるのでしょうか。ここでは、企業が傾聴力を評価する理由を3つ解説します。
それぞれの理由について見ていきましょう。
そのため同僚や上司・部下と円滑に関われて、チームワークの向上に役立ったり、業務の効率アップにも貢献したりするでしょう。
また、クライアントと直接関わる機会の多い営業職や販売職などの仕事の場合、傾聴力があることで良好な関係を築きやすく、契約の獲得や継続にも大きな役割を果たしやすいです。
このときに悩みを安心して話せる空気感を作れたり、相手の話から深掘りした質問ができたりする人だと、クライアントの本音を引き出しやすいでしょう。相手の求めるニーズを的確に捉えられれば、解決に導けるサービス提供ができるため、顧客満足度の向上にもつながります。
たとえば「顧客満足度が低下している」ことが企業の課題だとします。このときに傾聴力のある社員がいれば、顧客の声や従業員の意見を丁寧かつ的確に聞き取り、何が問題となっているのか導き出せるでしょう。
また、傾聴力があることで新しいアイデアや解決策が見つかることもあります。たとえばチームのプロジェクトが行き詰まった際に、メンバーの意見や本音を聞き出すことで、これまでになかった視点が生まれ、課題の解決につながることもあるでしょう。
このように傾聴力がある社員がいることで、チームや企業の問題解決につながることも期待されています。

傾聴力は、就職や転職活動でよく使われやすいアピールポイントです。そのため、伝え方に工夫する必要があります。 ここでは自己PRで傾聴力を効果的にアピールするためのコツ3つを紹介します。
そのため、一人ひとりの自己PRを細かく読んでくれるとは限りません。 選考倍率の高い人気のある企業の場合、少しでも内容が読みづらいとその時点で不採用になる可能性もあります。
そこで、内容が伝わりやすいような構成で自己PRを組み立てることが大切です。伝わりやすい構成のひとつに「PREP法」があります。PREP法は、以下のような順番で文章を構成する型のことです。
自己PRでは、具体例のところに根拠となるエピソードや企業での活かし方を伝えるのがおすすめです。職務経歴書の具体的な書き方やマナーについて知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
【関連記事:【例文あり】職務経歴書の書き方と提出方法・マナーを簡単に解説】
そこで、傾聴力と組み合わせやすい他の強みも加えて、より魅力的な自己PRを作成することをおすすめします。たとえば、傾聴力と課題解決力をセットでアピールするなら「クライアントの話を聞いて課題を見つけ出し、解決につなげられた」ということを説明するエピソードが効果的です。
このように他の強みも混ぜることで、採用担当者に傾聴力をポジティブなスキルとして伝えられます。「傾聴力と組み合わせやすい強み4つ」について後述していますので、こちらもぜひチェックしてみてください。
そのため、たとえば志望先が営業職なら、傾聴力に加えて行動力や目標達成への意欲などを伝えるのがいいでしょう。また、コンサルタント職なら傾聴力と課題解決力を組み合わせるのが効果的です。
このように企業のニーズや職種に合わせて自己PRの内容を調整することで、高評価につながりやすくなります。

自己PRで傾聴力を伝えるときは、以下の4つに注意しましょう。
それぞれについて詳しく解説します。
「傾聴力を活かして課題を発見し、継続受注を⚪︎件獲得した」のように傾聴力を発揮できた具体的なエピソードを伝えられると、オリジナリティのある自己PRができるはずです。
自己PRで「傾聴力がある」と伝えているにもかかわらず、面接官の話を集中して聞いていなかったり、うなずきや相槌などが少なかったりすると「本当に傾聴力がある人なのだろうか」と疑問に思われてしまうでしょう。
面接の場でも傾聴力を裏付けられれば、効果的にアピールできます。面接官から得た情報をもとに、より深掘りした逆質問などができると、評価につながりやすいです。
【関連記事:やる気と意欲が伝わる!転職時の面接に役立つおすすめの逆質問】
たとえば「傾聴力を活かして、クライアントの要望をヒアリングし、課題の解決につながった」などの実体験を伝えられれば、能動的な姿勢もアピールできます。

傾聴力は自己PRでよく使われるワードのため、採用担当者に「また傾聴力か…」と思われる可能性もあります。そのため、別のワードに言い換えることで他の希望者と差別化しやすくなるでしょう。
ここでは、傾聴力のおすすめ言い換えワードとして以下4つを紹介します。
そのため、傾聴力が高ければ相手の本音を引き出すことができるでしょう。ビジネスにおいて、クライアントの潜在的なニーズを引き出すのは、適切な商品を売るうえで欠かせません。
相手の本音を引き出せることは、顧客満足度や売上アップにもつながるため、企業にとっても魅力的に映るでしょう。
そのような場面で、他者の話や意見を聞いて課題を解決できた経験があれば、傾聴力があることに説得力を持たせられます。 たとえば、以下のような具体例が挙げられるでしょう。
このようにヒアリングを通して意見をまとめられることも、傾聴力として自己PRに活用できるといえます。
ビジネスにおいて重要なのは商品の質もそうですが「誰から買うか」です。 たとえば服屋で服を買うとき、探している商品についてしっかり話を聞いてくれる店員と、一方的におすすめのアイテムを押し売りしてくるような店員だと、前者から購入したいと思うでしょう。
信頼関係を築ける能力を欲している企業は多いため、効果的にアピールしていくことが大切です。
傾聴力はただ話を聞くだけではなく、相手に寄り添うことで安心して話せる空気感を作ることも求められます。そのため、共感力と共通する部分があるのです。
営業職や販売職など直接クライアントと接する機会が多い職種では、特に共感力が求められやすいので、共感力を発揮できた具体的なエピソードを語るといいでしょう。

他者と差別化するなら、傾聴力にマッチする他の強みを組み合わせることが大切です。ここでは傾聴力と一緒にアピールしやすい強み4つを紹介します。
課題の発見や原因を見つけるには、社内のメンバーやクライアントの話をヒアリングし深掘りする必要があります。そのため、傾聴力と合わせて活かせる強みとして自己PRできれば、よりアピールにつながるでしょう。
行動力を組み合わせる場合は、傾聴力を身につけた過程を説明するときに活用するのがおすすめ。「自分で目標達成に向けて行動したときに、傾聴力が身についた」のように、行動した結果で得たスキルとして自然にアピールできるでしょう。
たとえば「社内メンバーにヒアリングを行い、業務効率化のシステム導入を企画したところ、〇〇の時間を⚪%削減できた」という具体例を挙げると、傾聴力と企画力をまとめてアピールできるでしょう。
決断するうえでは他者の意見を聞くことが欠かせないため「話を聞いたうえで、その場において最適な決断ができる」ことをアピールできると、魅力的な自己PRになるでしょう。
以下記事では面接で使える強みを見つける方法や、伝え方のコツについて解説しています。こちらもあわせてご確認ください。
【関連記事:自分の強みとは?弱みも見つけて転職活動でうまくアピールする方法を紹介】
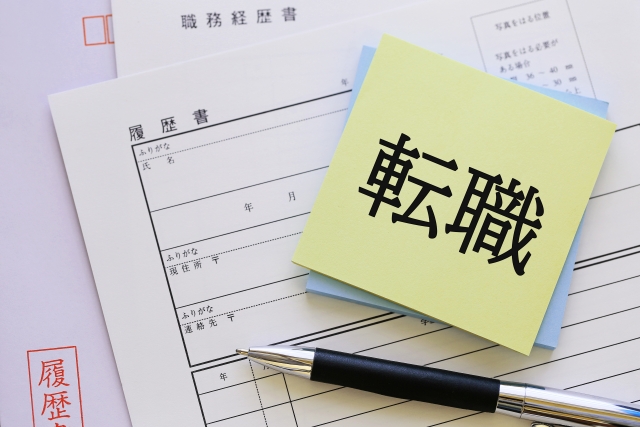
ここでは、自己PRで傾聴力をアピールするときの例文を以下の職種別に紹介します。
営業職において、傾聴力はクライアントの潜在的なニーズを聞き出すために不可欠です。実際に聞き出したニーズからどのような提案を行い、受注数や売上がどれぐらい変化したのか、具体的な数字を用いてアピールしましょう。
事務職は従業員のサポートを行うため、数字を用いた具体的な成果を表しづらいです。そのため、他部門の人とコミュニケーションをとるなかで傾聴力が活きた経験を伝えるのが効果的といえます。
エンジニア職は顧客折衝やマネジメントの経験から、傾聴力を活用して課題を解決できた経験をPRするといいでしょう。
販売職は顧客と直接やりとりする機会が多いため、工夫したことがわかる具体的なエピソードを伝えられれば、傾聴力をアピールできるでしょう。
技術職ではコミュニケーションで傾聴力が活きた経験や、ミスを減らした数といった定量的な成果をアピールするのがいいでしょう。
医療職の場合、患者との関わりから傾聴力を発揮したエピソードを盛り込むと、説得力のある自己PRにつながるでしょう。
クリエイティブ職の場合、クライアント対応時やチームで傾聴力が役立った経験が自己PRに活用できるでしょう。また、自分の作成した成果物でどのくらいの効果が出たのか、数字を用いてアピールできるとより効果的です。

自己PR文を考えているとき「自分の強みがわからない」と悩むこともあるでしょう。 効果的な自己PRを考えるなら、自己分析が欠かせません。
自己分析に苦手意識がある方は、転職サービス「ミイダス」の「コンピテンシー診断(特性診断)」を受けてみてください。
コンピテンシー診断(特性診断)は、仕事ができる従業員の特徴をもとに、自分がその仕事にどれくらい適性があるのか見極められるサービスのこと。専門家が監修しているため、学術的にも信頼できる診断サービスなのが特徴です。
コンピテンシー診断(特性診断)を受けると以下のようなカテゴリーからあなたの特性が数値で出てくるため、自分の強みを可視化できます。
たとえば、傾聴力がある人は「共感力」の数値が高くなるでしょう。また「マネジメントスタイル」の数値が高い場合、傾聴力と合わせて決断力や課題解決力などもアピールできるはずです。
コンピテンシー診断(特性診断)を受けることで、診断結果とマッチする企業からスカウトが届くこともあるので、自分に合った転職先を効率的に見つけられますよ。
ミイダスの登録やコンピテンシー診断(特性診断)の受検は無料でできるので、この機会にぜひ試してみてください。
\自分の強みや適性がわかる!/
ミイダスでコンピテンシー診断(特性診断)する

この記事では、傾聴力を自己PRでアピールするときのコツや注意点、職種別の例文などを紹介しました。 傾聴力は職種を問わず活かせるアピールポイントであるため、自己PRで人気を集めるテーマです。
一方で、他の転職希望者と被りやすいのが難点でもあります。 そこで、前職で傾聴力を活かした事例を具体的に説明したり、他の強みと合わせてアピールしたりしてオリジナル性の高いアピールを心がけることが大切です。
これまでの経験を振り返り、傾聴力が効果的に働いたエピソードを考えてみてください。 もし「自己分析がうまくできない」という場合は、ミイダスの「コンピテンシー診断(特性診断)」がおすすめです。
質問に対して答えをタップして回答していくだけで、あなたの上司・部下としての傾向やストレス要因など自分の特性がわかります。 自己分析にも役立つツールなので、試してみてください。
\自分の強みや適性がわかる!/
ミイダスでコンピテンシー診断(特性診断)する
「面接で差別化できるアピール方法を知りたい」
このように考えている方もいるのではないでしょうか。傾聴力は相手の話を聞いて、本音を引き出せるスキルのことを指します。
傾聴力は仕事での人間関係やスムーズな業務に役立つため、自己PRでアピールしたいと考えている方も多いです。しかし、アピールポイントになるぶん他の転職希望者と被りやすいスキルでもあるため、差別化して効果的に伝えるのが転職成功のカギになります。
この記事では、傾聴力がある人の特徴やうまくアピールするコツ、職種別の傾聴力があることを伝えられる自己PR例文7選を紹介します。転職時の自己PRで傾聴力をアピールしたい方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
「転職を考えているけれど、仕事選びで失敗したくない」
「自分の強みや向いている仕事を知りたい」
そんな方は、ミイダスの「コンピテンシー診断(特性診断)」を受けて自分に合った仕事を見つけましょう。
関連記事:転職できる?可能性診断ならミイダスの「コンピテンシー診断(特性診断)」
\自分の強みや適性がわかる!/ ミイダスでコンピテンシー診断(特性診断)する
「自分の強みや向いている仕事を知りたい」
そんな方は、ミイダスの「コンピテンシー診断(特性診断)」を受けて自分に合った仕事を見つけましょう。
関連記事:転職できる?可能性診断ならミイダスの「コンピテンシー診断(特性診断)」
※登録後に無料で診断できます。
傾聴力とは|相手の話を聞き、話を引き出すスキル

自己PRで活用できる傾聴力とは「相手の話をしっかり聞いて、相手が伝えたい話を引き出せるスキル」のことです。 傾聴力と聞くと「静かに話を聞く力」を指すことが多いです。
しかし、それだけでは受け身の印象を与えやすく、転職活動での効果的なアピールにはつながりづらいでしょう。 相手が気持ちよく話せるように適切なタイミングで相槌を打ったり、より掘り下げた質問ができたりと相手の話を引き出せる傾聴力があると、ビジネスにおいて信頼を築くのに役立ちます。
【関連記事:【長所別】面接で使える自己PRの例文5選|強みの見つけ方も紹介】
【当てはまる?】傾聴力がある人の特徴4つ

以下では傾聴力がある人の特徴を4つ紹介します。
- 共感力がある
- 相槌が得意である
- 話を引き出す質問ができる
- 相談相手になることが多い
「自分は本当に傾聴力があるのだろうか」と考えている人は、当てはまっていないか確認してみてください。
特徴①:共感力がある
傾聴力がある人は相手の気持ちを理解して、感情に寄り添える「共感力」を持ち合わせています。 共感力があると、相手の置かれている状況や悩みを自分の立場に置き換えて考えられます。その場の空気や相手のちょっとした仕草や表情を察知して、言葉にしていない感情を感じ取れるのも特徴です。
「自分も同じような経験があるから苦労がわかる」「これを伝えたら喜ぶだろうな」など、相手の感情を肯定できるため、話す側も安心して本心や悩みを語れて信頼関係につながりやすいです。
特徴②:相槌が得意である
相槌が得意なことも、傾聴力がある人が持つ要素のひとつです。相槌を打つことで「あなたの話を真剣に聞いている」「あなたの話に共感している」という意思表示ができます。- そうなんだ!
- なるほど〜
- よかったね、いいね
- (それから)どうなったの?
- わかる
同じ相槌ばかりではなく、上記のように話の内容によって適切な相槌を使い分けられると、相手は話を聞いてくれていると安心でき、会話も盛り上がるでしょう。
特徴③:話を引き出す質問ができる
相手の本音を引き出せる質問ができることも、傾聴力が高い人の特徴といえます。質問をすることで、相手に興味や関心があることを伝えられます。また、調べてわかるような質問をするのではなく、相手の話を掘り下げたり意見を尋ねたりする質問ができると、話している本人も気づいていなかった本音を引き出せるでしょう。 その結果、「この人とは話しやすい」「いろいろな気づきを得られて面白い」と思われやすくなります。
特徴④:相談相手になることが多い
傾聴力が高いと、人の相談にのることが増えやすいです。傾聴力がある人は、相手が求めているアドバイスやフィードバックに気づきやすく、それを適切なタイミングで伝えられます。そのため、相手も話を聞いてもらうことで思考が整理されたり、具体的な解決策を見つけられたりするでしょう。このように傾聴力がある人は「安心して相談できる人」と認識してもらいやすく、周囲から頼りにされる存在になることが多いです。
企業側が傾聴力を評価する3つの理由

ビジネスにおいて傾聴力が重視されるのには、どのような理由があるのでしょうか。ここでは、企業が傾聴力を評価する理由を3つ解説します。
- 人間関係を築くために欠かせないスキルのため
- 相手の本音を引き出せるため
- 課題や問題解決に役立つため
それぞれの理由について見ていきましょう。
理由①:人間関係を築くために欠かせないスキルのため
傾聴力は人間関係を築くために欠かせないスキルです。傾聴力がある社員は、相手の話を聞いて深く共感できるため、社内外で関わる人と信頼関係を築くのが得意といえます。そのため同僚や上司・部下と円滑に関われて、チームワークの向上に役立ったり、業務の効率アップにも貢献したりするでしょう。
また、クライアントと直接関わる機会の多い営業職や販売職などの仕事の場合、傾聴力があることで良好な関係を築きやすく、契約の獲得や継続にも大きな役割を果たしやすいです。
理由②:相手の本音を引き出せるため
相手の本音を引き出せる能力があることも、企業が傾聴力がある人を評価する理由のひとつです。たとえば営業職の場合、クライアントの話を聞くことで心の内にあるニーズを引き出し、適切な商品を提案することが求められます。このときに悩みを安心して話せる空気感を作れたり、相手の話から深掘りした質問ができたりする人だと、クライアントの本音を引き出しやすいでしょう。相手の求めるニーズを的確に捉えられれば、解決に導けるサービス提供ができるため、顧客満足度の向上にもつながります。
理由③:課題や問題解決に役に立つため
傾聴力は企業が抱えるさまざまな課題を、スピード感を持って効果的に解決するために欠かせないスキルです。たとえば「顧客満足度が低下している」ことが企業の課題だとします。このときに傾聴力のある社員がいれば、顧客の声や従業員の意見を丁寧かつ的確に聞き取り、何が問題となっているのか導き出せるでしょう。
また、傾聴力があることで新しいアイデアや解決策が見つかることもあります。たとえばチームのプロジェクトが行き詰まった際に、メンバーの意見や本音を聞き出すことで、これまでになかった視点が生まれ、課題の解決につながることもあるでしょう。
このように傾聴力がある社員がいることで、チームや企業の問題解決につながることも期待されています。
自己PRで傾聴力を効果的にアピールするコツ3選

傾聴力は、就職や転職活動でよく使われやすいアピールポイントです。そのため、伝え方に工夫する必要があります。 ここでは自己PRで傾聴力を効果的にアピールするためのコツ3つを紹介します。
- 伝わりやすい構成を意識する
- 傾聴力にマッチする他の強みもアピールする
- 企業のニーズや社風に合わせて内容を調整する
コツ①:伝わりやすい構成を意識する
自己PRで傾聴力があることをアピールするには、伝わりやすい構成を意識することが大切です。 採用担当者はあなた以外にも、たくさんの応募者の履歴書や職務経歴書を確認しています。そのため、一人ひとりの自己PRを細かく読んでくれるとは限りません。 選考倍率の高い人気のある企業の場合、少しでも内容が読みづらいとその時点で不採用になる可能性もあります。
そこで、内容が伝わりやすいような構成で自己PRを組み立てることが大切です。伝わりやすい構成のひとつに「PREP法」があります。PREP法は、以下のような順番で文章を構成する型のことです。
- 結論(Point)
- 理由(Reason)
- 具体例(Example)
- 再結論(Point)
自己PRでは、具体例のところに根拠となるエピソードや企業での活かし方を伝えるのがおすすめです。職務経歴書の具体的な書き方やマナーについて知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
【関連記事:【例文あり】職務経歴書の書き方と提出方法・マナーを簡単に解説】
コツ②:傾聴力にマッチする他の強みもアピールする
傾聴力と相性のいい他の強みを一緒にアピールするのも効果的な手法です。傾聴力は自己PRにも活用できるスキルですが、相手への伝わり方によっては「受け身な人」「聞き上手なだけ」などと捉えられる可能性もあります。そこで、傾聴力と組み合わせやすい他の強みも加えて、より魅力的な自己PRを作成することをおすすめします。たとえば、傾聴力と課題解決力をセットでアピールするなら「クライアントの話を聞いて課題を見つけ出し、解決につなげられた」ということを説明するエピソードが効果的です。
このように他の強みも混ぜることで、採用担当者に傾聴力をポジティブなスキルとして伝えられます。「傾聴力と組み合わせやすい強み4つ」について後述していますので、こちらもぜひチェックしてみてください。
コツ③:企業のニーズや職種に合わせて内容を調整する
自己PRを効果的に伝えるためには、企業のニーズや職種に合わせて内容を調整することも大切です。企業や職種によって求められている人材は異なるため、同じ自己PRを使い回してもアピールにつながるとは限りません。そのため、たとえば志望先が営業職なら、傾聴力に加えて行動力や目標達成への意欲などを伝えるのがいいでしょう。また、コンサルタント職なら傾聴力と課題解決力を組み合わせるのが効果的です。
このように企業のニーズや職種に合わせて自己PRの内容を調整することで、高評価につながりやすくなります。
自己PRで傾聴力を伝えるときの注意点3つ

自己PRで傾聴力を伝えるときは、以下の4つに注意しましょう。
- 他の人と被らないよう差別化する
- 面接でも傾聴力を発揮する
- 受け身な印象にならないようにする
それぞれについて詳しく解説します。
注意点①:他の人と被らないよう差別化する
自己PRで傾聴力があることを伝えるなら、他者と被らないように差別化するのがポイントです。傾聴力は自己PRでよく使われるアピールポイントのため、内容を差別化しないと採用担当者の目に留まらない可能性が高いでしょう。「傾聴力を活かして課題を発見し、継続受注を⚪︎件獲得した」のように傾聴力を発揮できた具体的なエピソードを伝えられると、オリジナリティのある自己PRができるはずです。
注意点②:面接でも傾聴力を発揮する
面接での立ち振る舞いや受け答えを徹底することによって、傾聴力があることを裏付けられます。自己PRで「傾聴力がある」と伝えているにもかかわらず、面接官の話を集中して聞いていなかったり、うなずきや相槌などが少なかったりすると「本当に傾聴力がある人なのだろうか」と疑問に思われてしまうでしょう。
面接の場でも傾聴力を裏付けられれば、効果的にアピールできます。面接官から得た情報をもとに、より深掘りした逆質問などができると、評価につながりやすいです。
【関連記事:やる気と意欲が伝わる!転職時の面接に役立つおすすめの逆質問】
注意点③:受け身な印象にならないようにする
傾聴力は「ただ話を聞くこと」と捉えられる可能性もあります。そのため、受け身な姿勢ではなく、主体性があることをアピールするのが大切です。 「自分の傾聴力を使って、成果につながる働きかけをした」というエピソードを伝えましょう。たとえば「傾聴力を活かして、クライアントの要望をヒアリングし、課題の解決につながった」などの実体験を伝えられれば、能動的な姿勢もアピールできます。
差別化できる!傾聴力の言い換えワード例

傾聴力は自己PRでよく使われるワードのため、採用担当者に「また傾聴力か…」と思われる可能性もあります。そのため、別のワードに言い換えることで他の希望者と差別化しやすくなるでしょう。
ここでは、傾聴力のおすすめ言い換えワードとして以下4つを紹介します。
- 他社の本音を引き出す力
- 意見をまとめる力
- 信頼関係構築力
- 共感力
他者の本音を引き出す力
転職で用いる傾聴力は「他者の本音を引き出す力」とも言い換えられます。適切なタイミングで相槌を打ってくれたり、共感の言葉をかけてくれたりすると「話を聞いてくれている」と安心でき、相手は積極的に会話をしたくなるものです。そのため、傾聴力が高ければ相手の本音を引き出すことができるでしょう。ビジネスにおいて、クライアントの潜在的なニーズを引き出すのは、適切な商品を売るうえで欠かせません。
相手の本音を引き出せることは、顧客満足度や売上アップにもつながるため、企業にとっても魅力的に映るでしょう。
意見をまとめる力
傾聴力があれば、一人ひとりの意見を尊重しつつ、客観的な視点から全体の話をまとめられます。 ビジネスにおいて、メンバーやクライアントとの意見が食い違うこともあるでしょう。そのような場面で、他者の話や意見を聞いて課題を解決できた経験があれば、傾聴力があることに説得力を持たせられます。 たとえば、以下のような具体例が挙げられるでしょう。
「〇〇のプロジェクトで、デザイン担当とマーケティング担当の間でターゲット層の解釈が異なり、進行が停滞したことがありました。 そこで双方の意見をヒアリングし、顧客のデータをもとに優先すべきターゲット層を明確化しました。
その結果、メンバー全員が同じ方向を向くことができ、スムーズにプロジェクトを進められた経験があります」
その結果、メンバー全員が同じ方向を向くことができ、スムーズにプロジェクトを進められた経験があります」
このようにヒアリングを通して意見をまとめられることも、傾聴力として自己PRに活用できるといえます。
信頼関係構築力
傾聴力は、人間関係を円滑に進めるうえで欠かせないスキルです。そのため「信頼関係構築力」とも言い換えられるでしょう。相手の話を親身に聞いて理解を示すことで、信頼関係が生まれていきます。ビジネスにおいて重要なのは商品の質もそうですが「誰から買うか」です。 たとえば服屋で服を買うとき、探している商品についてしっかり話を聞いてくれる店員と、一方的におすすめのアイテムを押し売りしてくるような店員だと、前者から購入したいと思うでしょう。
信頼関係を築ける能力を欲している企業は多いため、効果的にアピールしていくことが大切です。
共感力
傾聴力の言い換えワードのひとつに「共感力」があります。共感力は「他人の考えや意見に同意できたり、喜怒哀楽などの感情に寄り添ったりできるスキル」です。傾聴力はただ話を聞くだけではなく、相手に寄り添うことで安心して話せる空気感を作ることも求められます。そのため、共感力と共通する部分があるのです。
営業職や販売職など直接クライアントと接する機会が多い職種では、特に共感力が求められやすいので、共感力を発揮できた具体的なエピソードを語るといいでしょう。
傾聴力と組み合わせやすい強み4つ

他者と差別化するなら、傾聴力にマッチする他の強みを組み合わせることが大切です。ここでは傾聴力と一緒にアピールしやすい強み4つを紹介します。
- 課題解決力
- 行動力
- 企画力
- 決断力
①課題解決力
「課題解決力」は、傾聴力と組み合わせやすい強みのひとつです。これは、課題を特定しその原因や解決策を見つけ出す能力のことを指します。課題の発見や原因を見つけるには、社内のメンバーやクライアントの話をヒアリングし深掘りする必要があります。そのため、傾聴力と合わせて活かせる強みとして自己PRできれば、よりアピールにつながるでしょう。
②行動力
傾聴力と相性のいい強みとして「行動力」が挙げられます。行動力は、目標や目的を叶えるために必要なことを自分で考えられて、行動に移せる力のことです。行動力を組み合わせる場合は、傾聴力を身につけた過程を説明するときに活用するのがおすすめ。「自分で目標達成に向けて行動したときに、傾聴力が身についた」のように、行動した結果で得たスキルとして自然にアピールできるでしょう。
③企画力
「企画力」も傾聴力の+αのスキルとしてアピールできます。企画力は、課題を見つけて解決方法や実行までの道筋を立てられる力のことです。たとえば「社内メンバーにヒアリングを行い、業務効率化のシステム導入を企画したところ、〇〇の時間を⚪%削減できた」という具体例を挙げると、傾聴力と企画力をまとめてアピールできるでしょう。
④決断力
傾聴力と相性のいい能力として「決断力」も挙げられます。決断力は、自分の意思で物事の方針を考えたり行動できたりする力のことです。決断するうえでは他者の意見を聞くことが欠かせないため「話を聞いたうえで、その場において最適な決断ができる」ことをアピールできると、魅力的な自己PRになるでしょう。
以下記事では面接で使える強みを見つける方法や、伝え方のコツについて解説しています。こちらもあわせてご確認ください。
【関連記事:自分の強みとは?弱みも見つけて転職活動でうまくアピールする方法を紹介】
【職種別】自己PRで傾聴力をアピールする例文7選
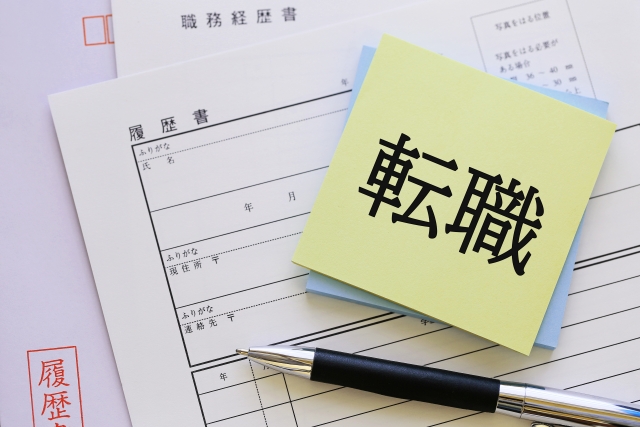
ここでは、自己PRで傾聴力をアピールするときの例文を以下の職種別に紹介します。
- 営業職
- 事務職
- エンジニア職
- 販売・サービス職
- 技術職
- 医療職
- クリエイティブ職
①営業職
「私は営業職として働くうえで傾聴力を大切にしていました。前職では法人営業を担当しており、クライアントの課題をより可視化するために詳細なヒアリングを行いました。
具体的には売上の低迷を相談された際に、商品ラインナップやターゲット層、競合状況を伺い、課題の根本原因を特定していました。結果として、顧客のニーズに合ったプランを提案し、年間契約額を30%アップを達成。
また、定期的なフォローを行い信頼関係を強化し、紹介による新規契約が全体の20%を占めるまでに成長しました。この傾聴力を活かし、貴社でもお客様の期待を超える提案を行い、売上に貢献したいと考えています」
具体的には売上の低迷を相談された際に、商品ラインナップやターゲット層、競合状況を伺い、課題の根本原因を特定していました。結果として、顧客のニーズに合ったプランを提案し、年間契約額を30%アップを達成。
また、定期的なフォローを行い信頼関係を強化し、紹介による新規契約が全体の20%を占めるまでに成長しました。この傾聴力を活かし、貴社でもお客様の期待を超える提案を行い、売上に貢献したいと考えています」
営業職において、傾聴力はクライアントの潜在的なニーズを聞き出すために不可欠です。実際に聞き出したニーズからどのような提案を行い、受注数や売上がどれぐらい変化したのか、具体的な数字を用いてアピールしましょう。
②事務職
「私の強みは傾聴力です。前職では営業部門を支える事務職として、営業担当者の要望や課題を丁寧に聞き取り、迅速かつ的確な対応を心がけてきました。
営業用の資料を作成する際には、担当者に必要な情報を事前にヒアリングし、相手の要望と私自身の認識に相違がないか確認しながら、最適な資料を作成できるよう努めてきました。
こうした姿勢を評価していただき、営業アシスタントとして新人教育や研修も担当しております。貴社でも傾聴力を活かし、〇〇部門で貢献していければと考えております」
営業用の資料を作成する際には、担当者に必要な情報を事前にヒアリングし、相手の要望と私自身の認識に相違がないか確認しながら、最適な資料を作成できるよう努めてきました。
こうした姿勢を評価していただき、営業アシスタントとして新人教育や研修も担当しております。貴社でも傾聴力を活かし、〇〇部門で貢献していければと考えております」
事務職は従業員のサポートを行うため、数字を用いた具体的な成果を表しづらいです。そのため、他部門の人とコミュニケーションをとるなかで傾聴力が活きた経験を伝えるのが効果的といえます。
③エンジニア職
「システムエンジニアとして働くなかで、傾聴を意識して業務を行っています。特にクライアントの要望を正確にヒアリングし、課題やニーズを的確に把握することを大切にしていました。
具体的には、現在のシステムに対する不満をクライアントから伺った際に、運用面に課題があることを発見しました。そこでUI/UXを改善した結果、操作性がアップし、結果的に作業効率が25%増加しました。
このように、傾聴力によって相手の要望や意図を正しく把握できることがクライアントへの貢献につながっており、私の強みだと考えております」
具体的には、現在のシステムに対する不満をクライアントから伺った際に、運用面に課題があることを発見しました。そこでUI/UXを改善した結果、操作性がアップし、結果的に作業効率が25%増加しました。
このように、傾聴力によって相手の要望や意図を正しく把握できることがクライアントへの貢献につながっており、私の強みだと考えております」
エンジニア職は顧客折衝やマネジメントの経験から、傾聴力を活用して課題を解決できた経験をPRするといいでしょう。
④販売・サービス職
「私の強みは傾聴力です。前職ではアパレル販売の仕事をしており、お客様一人ひとりの好みやライフスタイルをヒアリングして、最適な商品を提案することを心がけていました。
また、自主的に最新トレンドや素材の知識を勉強し、お客様の要望や好みにマッチする商品の提案を行いました。その結果、大変満足していただきリピーターとしてご来店いただいています。
入社後はこの傾聴力を活かして、お客様目線で最適な商品提案を行い、活躍したいと考えております」
また、自主的に最新トレンドや素材の知識を勉強し、お客様の要望や好みにマッチする商品の提案を行いました。その結果、大変満足していただきリピーターとしてご来店いただいています。
入社後はこの傾聴力を活かして、お客様目線で最適な商品提案を行い、活躍したいと考えております」
販売職は顧客と直接やりとりする機会が多いため、工夫したことがわかる具体的なエピソードを伝えられれば、傾聴力をアピールできるでしょう。
⑤技術職
「私は製造設備の保守管理を担当するなかで、傾聴力を特に重視しておりました。具体的には、現場のスタッフやクライアントの声を聞き、設備の改善点や不具合の把握に大きく役立った経験があります。
たとえば、現場社員にヒアリングしたとき『操作が難しくミスが起きやすい』という意見がありました。そこで、マニュアルの改訂や教育システムの見直しを提案。結果として操作ミスが30%減少し、作業効率もアップしました。
このように、現職で培った傾聴力を活かして貴社でも貢献したいです」
たとえば、現場社員にヒアリングしたとき『操作が難しくミスが起きやすい』という意見がありました。そこで、マニュアルの改訂や教育システムの見直しを提案。結果として操作ミスが30%減少し、作業効率もアップしました。
このように、現職で培った傾聴力を活かして貴社でも貢献したいです」
技術職ではコミュニケーションで傾聴力が活きた経験や、ミスを減らした数といった定量的な成果をアピールするのがいいでしょう。
⑥医療職
「私は傾聴力が自身の強みだと考えております。前職は調剤薬局で働いており、仕事において患者様一人ひとりの症状や不安に寄り添い、丁寧なヒアリングと薬剤情報や生活習慣のアドバイスを心がけていました。
患者様からは『〇〇さんと話すと安心できる』『話しやすい』という声をいただくことが増え、信頼関係を築くことができました。この傾聴力を活かして、貢献したいと考えております」
患者様からは『〇〇さんと話すと安心できる』『話しやすい』という声をいただくことが増え、信頼関係を築くことができました。この傾聴力を活かして、貢献したいと考えております」
医療職の場合、患者との関わりから傾聴力を発揮したエピソードを盛り込むと、説得力のある自己PRにつながるでしょう。
⑦クリエイティブ職
「私はデザイナーとして働くなかで、傾聴力を用いてクライアントの要望や課題を聞き、潜在的なニーズを聞き出すことを重視していました。 クライアントからは『可愛い感じにしてほしい』『おしゃれな雰囲気に』といった抽象的なデザイン依頼をいただくことが多いです。
そのため、当初は『何を求められてるのかわからない』と悩んだことがありました。 しかし、クライアントが求めていることを丁寧に聞き取ることで求められるデザインを制作できるようになりました。
その結果、⚪︎件のリピート案件を受注しております。この傾聴力を活かして、自分本位ではなくクライアントファーストの成果物を生み出したいと考えています」
そのため、当初は『何を求められてるのかわからない』と悩んだことがありました。 しかし、クライアントが求めていることを丁寧に聞き取ることで求められるデザインを制作できるようになりました。
その結果、⚪︎件のリピート案件を受注しております。この傾聴力を活かして、自分本位ではなくクライアントファーストの成果物を生み出したいと考えています」
クリエイティブ職の場合、クライアント対応時やチームで傾聴力が役立った経験が自己PRに活用できるでしょう。また、自分の作成した成果物でどのくらいの効果が出たのか、数字を用いてアピールできるとより効果的です。
自己PRに使える強みを見つけるなら「ミイダス」

自己PR文を考えているとき「自分の強みがわからない」と悩むこともあるでしょう。 効果的な自己PRを考えるなら、自己分析が欠かせません。
自己分析に苦手意識がある方は、転職サービス「ミイダス」の「コンピテンシー診断(特性診断)」を受けてみてください。
コンピテンシー診断(特性診断)は、仕事ができる従業員の特徴をもとに、自分がその仕事にどれくらい適性があるのか見極められるサービスのこと。専門家が監修しているため、学術的にも信頼できる診断サービスなのが特徴です。
コンピテンシー診断(特性診断)を受けると以下のようなカテゴリーからあなたの特性が数値で出てくるため、自分の強みを可視化できます。
- パーソナリティの傾向
- 上司・部下としての傾向
- ストレス要因
たとえば、傾聴力がある人は「共感力」の数値が高くなるでしょう。また「マネジメントスタイル」の数値が高い場合、傾聴力と合わせて決断力や課題解決力などもアピールできるはずです。
コンピテンシー診断(特性診断)を受けることで、診断結果とマッチする企業からスカウトが届くこともあるので、自分に合った転職先を効率的に見つけられますよ。
ミイダスの登録やコンピテンシー診断(特性診断)の受検は無料でできるので、この機会にぜひ試してみてください。
ミイダスでコンピテンシー診断(特性診断)する
※登録後に無料で診断できます。
自己PRで傾聴力をアピールするなら「差別化」を意識しよう!

この記事では、傾聴力を自己PRでアピールするときのコツや注意点、職種別の例文などを紹介しました。 傾聴力は職種を問わず活かせるアピールポイントであるため、自己PRで人気を集めるテーマです。
一方で、他の転職希望者と被りやすいのが難点でもあります。 そこで、前職で傾聴力を活かした事例を具体的に説明したり、他の強みと合わせてアピールしたりしてオリジナル性の高いアピールを心がけることが大切です。
これまでの経験を振り返り、傾聴力が効果的に働いたエピソードを考えてみてください。 もし「自己分析がうまくできない」という場合は、ミイダスの「コンピテンシー診断(特性診断)」がおすすめです。
質問に対して答えをタップして回答していくだけで、あなたの上司・部下としての傾向やストレス要因など自分の特性がわかります。 自己分析にも役立つツールなので、試してみてください。
ミイダスでコンピテンシー診断(特性診断)する
※登録後に無料で診断できます。


