目次
「円満退職するために最適なタイミングを知りたい」
「法律や就業規則上のルールを把握しておきたい」
このように考えている方もいるのではないでしょうか。退職を決意したものの、いつ、誰に、どのように伝えればいいのかや、どんな準備が必要なのか悩む方は少なくありません。
円満に退職し、次のステップへ気持ちよく進むためには、正しいタイミングで意思を伝えて、計画的に準備を進めることが非常に重要です。
この記事では、退職を伝える理想的なタイミングや、退職に必要な8ステップ、円満退社を実現するためのポイントまで詳しく解説します。 退職で後悔しないためにも、記事の内容をぜひ参考にしてください。
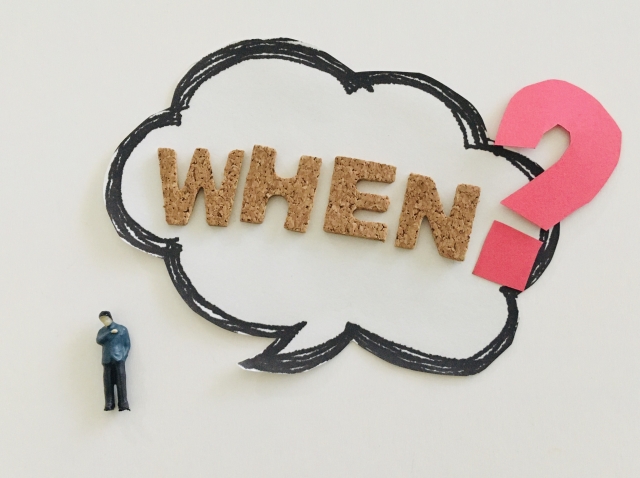
退職を伝えるタイミングは、雇用形態によって異なります。法律や会社の就業規則を確認し、円満な退職を目指しましょう。 ここでは、以下3つの雇用形態別に適切なタイミングを解説します。
多くの企業では、退職希望日の1〜3ヶ月前までに申し出るよう規定されています。 法律上では「いつでも退職を伝えられる」とされていますが、業務の引き継ぎや後任者の選定・教育などの時間を考慮し、できれば1ヶ月以上前に伝えるのが理想的といえるでしょう。
参考:民法 | e-Gov 法令検索
やむを得ない理由の例は以下のとおりです。
やむを得ない理由がある場合は、派遣元会社や契約先の企業に相談し、合意を得る必要があります。また、契約期間満了をもって退職する場合は、契約更新の意思確認が行われるタイミングで、更新しない旨を伝えるのが一般的です。
契約書や就業規則に退職に関する規定がある場合は、事前に確認しておきましょう。一方的に契約解除を申し出るのはトラブルの原因となるため避けるべきです。
参考:民法 | e-Gov 法令検索
特に、シフト制で働いている人は、急に退職することで職場が混乱する恐れもあるでしょう。 そのため、少なくとも1ヶ月前までに退職の意思を伝えるのがおすすめです。
店長や上司に相談し、退職日や最終出勤日、引き継ぎなどについて話し合いましょう。
民法では「2週間前の申し出で退職ができる」と定めていますが、これはあくまで法律上の話。退職希望日の直前に辞めることを伝えると、「非常識」と捉えられかねません。
実際には、就業規則で1ヶ月前やそれ以上の期間を定めている企業が多く、円満な退職を目指すのであれば、就業規則に従うのがよいでしょう。お世話になった会社や同僚への配慮として、できる限り早めに伝えることが、円満退社の鍵となります。

退職を決意してから実際に退職するまでの必要な行動や期間を把握しておくことで、計画的に進めやすくなるでしょう。ここでは、退職までの主なスケジュールを紹介します。
この期間に、退職願や退職届の提出を求められることもあります。上司との面談では、退職理由や退職希望日、感謝の気持ちを明確に伝えることが大切です。
1週間ほどで終わる場合もあれば、1ヶ月以上かかることもあるでしょう。 後任者がスムーズに業務を開始できるように、口頭での説明だけでなく、引き継ぎ資料の作成やOJTなどを行うのもおすすめです。
退職日までに未完了の業務がないよう、タスクをリストアップして進捗を管理することも重要といえます。
まとめて取得する場合は、最終出勤日を早めることも可能です。ただし、業務の引き継ぎに支障が出ないように配慮しましょう。企業によっては買い取り制度がある場合もありますが、基本的には消化することが多いです。

退職を決意してから実際に会社を辞めるまでに、踏むべきステップがあります。それぞれのステップを丁寧に進めることで、円満退社につながるでしょう。
「新しい分野に挑戦したい」「キャリアアップを目指したい」といった前向きな理由を伝えるのが望ましいです。ただし、嘘の退職理由を伝える必要はありません。
正直かつ相手に配慮した伝え方を心がけることが大切です。 上司に納得してもらい、応援してもらえるような理由であれば、円満な退職につながりやすくなります。
【関連記事:パワハラが理由の転職活動を成功させるには?退職理由の言い換えなど、ポイントを解説】
【関連記事:【例文あり】仕事を辞める理由と伝え方|円満退社するポイント5つも紹介】
法律では2週間前の申し出で退職可能とされていますが、円満退社のためには会社のルールに従うのが基本です。退職に関して不明な点があれば、人事担当者に確認してみてください。
上司に「ご相談したいことがあるのですが、少々お時間をいただけますでしょうか」などと伝え、個別に話せる時間を設けてもらいます。会議室や来客室といった他の人に聞かれない場所で、落ち着いて話せる環境を選ぶことが大切です。
アポイントを取るときは、メールや電話ではなく対面で伝えるのが基本ですが、状況に応じて適切な方法を選びましょう。
「退職願」は退職を願い出る書類で、会社が承諾して初めて退職が確定します。一方、「退職届」は退職するという確定的な意思を伝える書類です。
一般的には、まず退職願を提出し、退職日などが正式に決定したあとに退職届を提出するケースが多いですが、会社によって異なるため確認が必要です。 提出時期や書式、テンプレートについても就業規則を確認しましょう。
口頭で説明するだけでなく、誰が見てもわかるような引き継ぎ資料やマニュアルを作成するのがおすすめです。スケジュールを立て、計画的に進めることで、引き継ぎ漏れを防げます。
もし後任者が決まっていない場合は、上司に相談して、業務資料を残すなどの対応を検討しましょう。
また、お世話になった社内外の関係者やクライアントへ、退職の挨拶を直接またはメールで行いましょう。最終出勤日には、改めて部署のメンバーに挨拶をすることが大切です。
返却漏れがないように、リストを作成して確認するのもおすすめです。個人情報や機密情報が含まれる書類やデータは、会社の指示に従って適切に処理・削除しましょう。
これらは、失業保険の給付手続きや転職先での年末調整、国民年金・国民健康保険への切り替え手続きなどに必要です。退職日までに受け取れるか、後日郵送されるのかなどを事前に確認しておきましょう。
その他、会社によっては「離職票」や「退職証明書」などが発行されます。

お世話になった会社を円満に退職するためには、タイミングや伝え方以外にもいくつか押さえておきたいポイントがあります。これらのポイントを意識することで、良好な関係を保ったまま次のステップへ進めるでしょう。
繁忙期は人手が不足しやすく、一人でも欠けると他の社員の負担が大きくなります。業界や職種によって繁忙期は異なりますが、たとえば連休前や年度末などは忙しくなりやすいでしょう。
自分の業務状況やチームの業務量を考慮し、比較的落ち着いている時期を選ぶことで、会社への配慮を示せます。
ボーナスの査定期間や支給時期とも関連することがあるため、自身の待遇面も考慮しつつ、会社にとっても影響が少ないタイミングを選ぶことで円満退社につながるでしょう。
また、内定先への入社日が決まっていれば、退職希望日も具体的に伝えやすく、交渉もスムーズに進みやすいです。焦らずに次のステップが決まってから、行動に移しましょう。
【関連記事:【平日休めない人必見】在職中に転職の面接をするコツ5つやメール例文を紹介】

退職のタイミングに関して、よくある質問とその回答をまとめました。不安や疑問点がある方は、チェックしておきましょう。
しかし、稀に強い引き止めに合ったり、実質的に拒否されたりするケースもあります。その場合は、まず就業規則に反していないことを確認しつつ、退職の意思を明確にして「退職届」といった書面で再度伝えましょう。
それでも解決しない場合は、労働基準監督署や弁護士などの専門機関に相談することを検討してみてください。
そのため、ボーナスを受け取ってから退職を申し出る、もしくは支給日以降を退職日に設定するのがおすすめです。退職金についても、勤続年数や退職理由によって支給額が変動することがあります。
就業規則を確認し、不明な点は人事担当者に確認して、自身の不利益にならないタイミングを検討しましょう。
【関連記事:ボーナス支給日はいつ?一般的な支給日や退職・転職する際のベストなタイミングを解説】
会社との合意が得られれば、2週間を待たずに退職できることもあるでしょう。 難しい場合は、退職代行サービスを利用したり、医師の診断書を提出したりすることも一つの方法です。
無断欠勤や一方的な退職はトラブルの原因となるため、避けたほうが無難です。
【関連記事:仕事をすぐ辞めても大丈夫?甘えじゃない?メリットとデメリットを紹介】

この記事では、退職の適切なタイミングや円満退社するためのポイントなどを解説しました。
会社をあと腐れなく辞めるには、退職時期や伝え方を工夫することが大切です。また、次の職場が決まってから辞めることで、会社から引き止められにくく、スムーズに退職できるでしょう。
もし、在職期間で転職活動を進めるなら「ミイダス」の利用がおすすめです。 ミイダスは、求職者と企業のマッチングを重視した転職サービスです。
あなたの市場価値を診断して、活躍できる可能性が高い企業から直接スカウトが受け取れます。 「コンピテンシー診断(特性診断)」を受ければ、自分の適性や強みを把握できるため、自分に合った職場選びに役立つでしょう。
ミイダスの登録や各種サービスの利用はすべて無料です。自分らしいキャリアを築きたいと考えている方は、一度ミイダスを試してみてはいかがでしょうか。
\自分の強みや適性がわかる!/
ミイダスでコンピテンシー診断(特性診断)する
「法律や就業規則上のルールを把握しておきたい」
このように考えている方もいるのではないでしょうか。退職を決意したものの、いつ、誰に、どのように伝えればいいのかや、どんな準備が必要なのか悩む方は少なくありません。
円満に退職し、次のステップへ気持ちよく進むためには、正しいタイミングで意思を伝えて、計画的に準備を進めることが非常に重要です。
この記事では、退職を伝える理想的なタイミングや、退職に必要な8ステップ、円満退社を実現するためのポイントまで詳しく解説します。 退職で後悔しないためにも、記事の内容をぜひ参考にしてください。
「転職を考えているけれど、仕事選びで失敗したくない」
「自分の強みや向いている仕事を知りたい」
そんな方は、ミイダスの「コンピテンシー診断(特性診断)」を受けて自分に合った仕事を見つけましょう。
関連記事:転職できる?可能性診断ならミイダスの「コンピテンシー診断(特性診断)」
\自分の強みや適性がわかる!/ ミイダスでコンピテンシー診断(特性診断)する
「自分の強みや向いている仕事を知りたい」
そんな方は、ミイダスの「コンピテンシー診断(特性診断)」を受けて自分に合った仕事を見つけましょう。
関連記事:転職できる?可能性診断ならミイダスの「コンピテンシー診断(特性診断)」
※登録後に無料で診断できます。
【雇用形態別】退職を伝えるタイミング
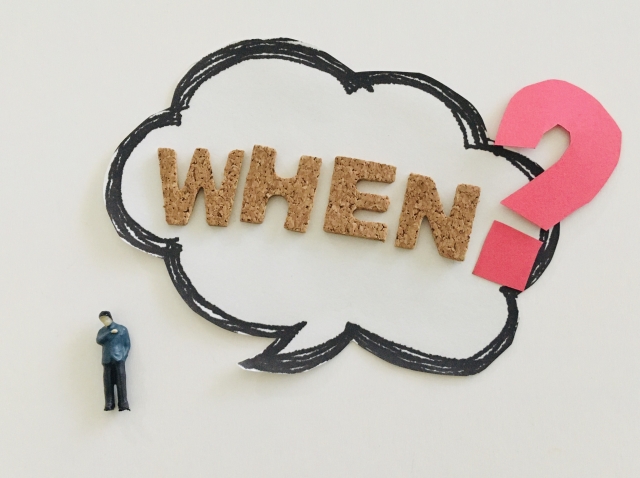
退職を伝えるタイミングは、雇用形態によって異なります。法律や会社の就業規則を確認し、円満な退職を目指しましょう。 ここでは、以下3つの雇用形態別に適切なタイミングを解説します。
- 正社員
- 派遣・契約社員
- パート・アルバイト
正社員の場合
正社員の場合は、民法第627条で雇用期間に定めがない場合、いつ退職の意思を伝えてもよく、意思表示から2週間が経てば雇用契約を終了できると決まっています。 しかし、円満退社をするためには会社の就業規則に従って退職をするのがおすすめです。多くの企業では、退職希望日の1〜3ヶ月前までに申し出るよう規定されています。 法律上では「いつでも退職を伝えられる」とされていますが、業務の引き継ぎや後任者の選定・教育などの時間を考慮し、できれば1ヶ月以上前に伝えるのが理想的といえるでしょう。
参考:民法 | e-Gov 法令検索
派遣・契約社員の場合
派遣社員や契約社員の場合、原則として契約期間中の退職はできません。しかし、民法628条で、やむを得ない理由があるならいつでも退職できると決められています。やむを得ない理由の例は以下のとおりです。
- 契約内容と業務内容が大きく異なる
- 賃金が支払われない
- パワハラやセクハラなどのハラスメントを受けている
- 家族や親族の介護や看病が必要になった
- 自分自身の体調が悪化した
- 遠方に引っ越すなどで通勤が難しくなった
やむを得ない理由がある場合は、派遣元会社や契約先の企業に相談し、合意を得る必要があります。また、契約期間満了をもって退職する場合は、契約更新の意思確認が行われるタイミングで、更新しない旨を伝えるのが一般的です。
契約書や就業規則に退職に関する規定がある場合は、事前に確認しておきましょう。一方的に契約解除を申し出るのはトラブルの原因となるため避けるべきです。
参考:民法 | e-Gov 法令検索
パート・アルバイトの場合
パート・アルバイトも正社員と同様で、退職希望日から2週間前に申し出れば退職できます。しかし、突然退職すると他のスタッフに迷惑をかける可能性が高いです。特に、シフト制で働いている人は、急に退職することで職場が混乱する恐れもあるでしょう。 そのため、少なくとも1ヶ月前までに退職の意思を伝えるのがおすすめです。
店長や上司に相談し、退職日や最終出勤日、引き継ぎなどについて話し合いましょう。
退職は2〜3ヶ月前に伝えるのがベスト!
退職の意思を伝えるタイミングとして、一般的には「2〜3ヶ月前」がベストとされています。あなたの退職日までの2〜3ヶ月で、企業側は後任者の採用や業務の引き継ぎを行うからです。民法では「2週間前の申し出で退職ができる」と定めていますが、これはあくまで法律上の話。退職希望日の直前に辞めることを伝えると、「非常識」と捉えられかねません。
実際には、就業規則で1ヶ月前やそれ以上の期間を定めている企業が多く、円満な退職を目指すのであれば、就業規則に従うのがよいでしょう。お世話になった会社や同僚への配慮として、できる限り早めに伝えることが、円満退社の鍵となります。
退職までの主なスケジュール

退職を決意してから実際に退職するまでの必要な行動や期間を把握しておくことで、計画的に進めやすくなるでしょう。ここでは、退職までの主なスケジュールを紹介します。
- 社内承認を得る(1〜2週間程度)
- 業務の引き継ぎをする(1週間〜1ヶ月程度)
- 有給休暇の消化をする(数日〜1ヶ月程度)
①社内承認を得る(1〜2週間程度)
直属の上司に退職の意思を伝えて、人事部やさらに上の役職者への報告・承認手続きが行われます。企業の規模や体制によって異なりますが、1〜2週間程度で正式な退職日が決定することが多いです。この期間に、退職願や退職届の提出を求められることもあります。上司との面談では、退職理由や退職希望日、感謝の気持ちを明確に伝えることが大切です。
②業務の引き継ぎをする(1週間〜1ヶ月程度)
退職日が正式に決まったら、後任者や他の担当者へ業務の引き継ぎを行います。引き継ぎに必要な期間は、業務内容や量によって大きく異なります。1週間ほどで終わる場合もあれば、1ヶ月以上かかることもあるでしょう。 後任者がスムーズに業務を開始できるように、口頭での説明だけでなく、引き継ぎ資料の作成やOJTなどを行うのもおすすめです。
退職日までに未完了の業務がないよう、タスクをリストアップして進捗を管理することも重要といえます。
③有給休暇の消化をする(数日〜1ヶ月程度)
残っている有給休暇は、退職日までに消化できます。有給休暇の残日数や業務の引き継ぎ状況、会社の繁忙期などを考慮し、上司と相談しながら有給消化の計画を立てましょう。まとめて取得する場合は、最終出勤日を早めることも可能です。ただし、業務の引き継ぎに支障が出ないように配慮しましょう。企業によっては買い取り制度がある場合もありますが、基本的には消化することが多いです。
退職に必要な8ステップ

退職を決意してから実際に会社を辞めるまでに、踏むべきステップがあります。それぞれのステップを丁寧に進めることで、円満退社につながるでしょう。
- 明確で前向きな退職理由を考える
- 退職のルールについて、就業規則で確認する
- 直属の上司にアポイントを取って伝える
- 退職願・退職届を提出する
- 業務の引き継ぎを行う
- 引き継ぎ後は周囲のサポートや挨拶を行う
- 荷物の整理や貸与物を返却する
- 必要な書類を受け取る
ステップ①明確で前向きな退職理由を考える
退職を決意したら、明確な退職理由を準備しておくことが重要です。その際、会社の不満や人間関係のトラブルなどが原因だったとしても、ストレートに伝えるのは避けましょう。「新しい分野に挑戦したい」「キャリアアップを目指したい」といった前向きな理由を伝えるのが望ましいです。ただし、嘘の退職理由を伝える必要はありません。
正直かつ相手に配慮した伝え方を心がけることが大切です。 上司に納得してもらい、応援してもらえるような理由であれば、円満な退職につながりやすくなります。
【関連記事:パワハラが理由の転職活動を成功させるには?退職理由の言い換えなど、ポイントを解説】
【関連記事:【例文あり】仕事を辞める理由と伝え方|円満退社するポイント5つも紹介】
ステップ②退職のルールについて、就業規則で確認する
退職の意思を伝える前に、必ず会社の就業規則を確認しましょう。就業規則には、退職を申し出る期限や、退職願や退職届の提出方法、その他の退職に関する手続きなどが記載されています。法律では2週間前の申し出で退職可能とされていますが、円満退社のためには会社のルールに従うのが基本です。退職に関して不明な点があれば、人事担当者に確認してみてください。
ステップ③直属の上司にアポイントを取って伝える
退職の意思は、まず直属の上司に伝えるのがマナーです。いきなり人事部や他の役職者に伝えるのは避けましょう。上司に「ご相談したいことがあるのですが、少々お時間をいただけますでしょうか」などと伝え、個別に話せる時間を設けてもらいます。会議室や来客室といった他の人に聞かれない場所で、落ち着いて話せる環境を選ぶことが大切です。
アポイントを取るときは、メールや電話ではなく対面で伝えるのが基本ですが、状況に応じて適切な方法を選びましょう。
ステップ④退職願・退職届を提出する
上司に退職の意思を伝えて承認を得られたら、会社の規定に従って退職願または退職届を提出します。「退職願」は退職を願い出る書類で、会社が承諾して初めて退職が確定します。一方、「退職届」は退職するという確定的な意思を伝える書類です。
一般的には、まず退職願を提出し、退職日などが正式に決定したあとに退職届を提出するケースが多いですが、会社によって異なるため確認が必要です。 提出時期や書式、テンプレートについても就業規則を確認しましょう。
ステップ⑤業務の引き継ぎを行う
退職日までに、担当していた業務を後任者や他の担当者に引き継ぎます。引き継ぎを行うことは退職者の役目であるため、誠意を持って対応しましょう。口頭で説明するだけでなく、誰が見てもわかるような引き継ぎ資料やマニュアルを作成するのがおすすめです。スケジュールを立て、計画的に進めることで、引き継ぎ漏れを防げます。
もし後任者が決まっていない場合は、上司に相談して、業務資料を残すなどの対応を検討しましょう。
ステップ⑥引き継ぎ後は周囲のサポートや挨拶を行う
業務の引き継ぎが完了したあとも、退職日までは会社の一員としての自覚を持ち、周囲の業務が円滑に進むようにサポートすることが大切です。後任者からの質問に丁寧に対応したり、他のメンバーの業務を手伝ったりすることで、感謝の気持ちを伝えられます。また、お世話になった社内外の関係者やクライアントへ、退職の挨拶を直接またはメールで行いましょう。最終出勤日には、改めて部署のメンバーに挨拶をすることが大切です。
ステップ⑦荷物の整理や貸与物を返却する
最終出勤日までに、デスク周りやロッカーなどにある私物の整理や回収を行います。会社から貸与されている以下のような備品はすべて返却しましょう。- 健康保険証
- 社員証
- 名刺
- パソコン
- 制服
- 業務関連の書類
- その他の備品
返却漏れがないように、リストを作成して確認するのもおすすめです。個人情報や機密情報が含まれる書類やデータは、会社の指示に従って適切に処理・削除しましょう。
ステップ⑧必要な書類を受け取る
退職時には、会社からいくつかの書類を受け取る必要があります。主な書類としては、以下が挙げられるでしょう。- 雇用保険被保険者証
- 年金手帳
- 源泉徴収票
- 健康保険資格喪失証明書
これらは、失業保険の給付手続きや転職先での年末調整、国民年金・国民健康保険への切り替え手続きなどに必要です。退職日までに受け取れるか、後日郵送されるのかなどを事前に確認しておきましょう。
その他、会社によっては「離職票」や「退職証明書」などが発行されます。
円満退職するために押さえておきたいポイント3つ

お世話になった会社を円満に退職するためには、タイミングや伝え方以外にもいくつか押さえておきたいポイントがあります。これらのポイントを意識することで、良好な関係を保ったまま次のステップへ進めるでしょう。
- 繁忙期の退職は避ける
- 期末や四半期末の前に伝える
- 内定をもらってから退職を伝える
①繁忙期の退職は避ける
円満退職するためには、退職の旨を伝えるタイミングが重要です。会社の繁忙期に退職を申し出たり退職したりするのは、できる限り避けるのがマナーです。繁忙期は人手が不足しやすく、一人でも欠けると他の社員の負担が大きくなります。業界や職種によって繁忙期は異なりますが、たとえば連休前や年度末などは忙しくなりやすいでしょう。
自分の業務状況やチームの業務量を考慮し、比較的落ち着いている時期を選ぶことで、会社への配慮を示せます。
②期末や四半期末の前に伝える
会社の会計年度や評価期間の区切りとなる期末や四半期末は、業務の締めや人事異動のタイミングと重なりやすいです。そのため、これらの時期の直前に退職の意思を伝えることで、会社側も後任者の選定や人員配置の計画を立てやすくなります。ボーナスの査定期間や支給時期とも関連することがあるため、自身の待遇面も考慮しつつ、会社にとっても影響が少ないタイミングを選ぶことで円満退社につながるでしょう。
③内定をもらってから退職を伝える
転職を理由に退職する場合、次の職場の内定を得てから退職の意思を伝えるのがおすすめです。内定を得る前に退職を伝えてしまうと、万が一転職活動がうまくいかなかった場合に、職を失ってしまうリスクがあります。また、内定先への入社日が決まっていれば、退職希望日も具体的に伝えやすく、交渉もスムーズに進みやすいです。焦らずに次のステップが決まってから、行動に移しましょう。
【関連記事:【平日休めない人必見】在職中に転職の面接をするコツ5つやメール例文を紹介】
【Q&A】退職のタイミングに関するよくある質問

退職のタイミングに関して、よくある質問とその回答をまとめました。不安や疑問点がある方は、チェックしておきましょう。
- 退職を拒否された場合はどうしたらいい?
- ボーナスや退職金をもらうなら、いつ退職するのがベスト?
- どうしてもすぐに辞めたい場合はどうすればいい?
退職を拒否された場合はどうしたらいい?
法律上、労働者には退職の自由があります。そのため、正当な理由なく会社側が退職を拒否することはできません。しかし、稀に強い引き止めに合ったり、実質的に拒否されたりするケースもあります。その場合は、まず就業規則に反していないことを確認しつつ、退職の意思を明確にして「退職届」といった書面で再度伝えましょう。
それでも解決しない場合は、労働基準監督署や弁護士などの専門機関に相談することを検討してみてください。
ボーナスや退職金をもらうなら、いつ退職するのがベスト?
ボーナスや退職金の支給条件や算定期間は、会社の就業規則などによって定められています。一般的に、ボーナスは支給日に在籍していることが条件となる場合が多いです。そのため、ボーナスを受け取ってから退職を申し出る、もしくは支給日以降を退職日に設定するのがおすすめです。退職金についても、勤続年数や退職理由によって支給額が変動することがあります。
就業規則を確認し、不明な点は人事担当者に確認して、自身の不利益にならないタイミングを検討しましょう。
【関連記事:ボーナス支給日はいつ?一般的な支給日や退職・転職する際のベストなタイミングを解説】
どうしてもすぐに辞めたい場合はどうすればいい?
心身の健康上の理由やハラスメントなど、やむを得ない事情でどうしてもすぐに会社を辞めたい場合もあるでしょう。 法律上は2週間前の申し出で退職できます。まずは直属の上司に事情を説明し、相談することが大切です。会社との合意が得られれば、2週間を待たずに退職できることもあるでしょう。 難しい場合は、退職代行サービスを利用したり、医師の診断書を提出したりすることも一つの方法です。
無断欠勤や一方的な退職はトラブルの原因となるため、避けたほうが無難です。
【関連記事:仕事をすぐ辞めても大丈夫?甘えじゃない?メリットとデメリットを紹介】
自分に合った環境で働くなら「ミイダス」がおすすめ!

この記事では、退職の適切なタイミングや円満退社するためのポイントなどを解説しました。
会社をあと腐れなく辞めるには、退職時期や伝え方を工夫することが大切です。また、次の職場が決まってから辞めることで、会社から引き止められにくく、スムーズに退職できるでしょう。
もし、在職期間で転職活動を進めるなら「ミイダス」の利用がおすすめです。 ミイダスは、求職者と企業のマッチングを重視した転職サービスです。
あなたの市場価値を診断して、活躍できる可能性が高い企業から直接スカウトが受け取れます。 「コンピテンシー診断(特性診断)」を受ければ、自分の適性や強みを把握できるため、自分に合った職場選びに役立つでしょう。
ミイダスの登録や各種サービスの利用はすべて無料です。自分らしいキャリアを築きたいと考えている方は、一度ミイダスを試してみてはいかがでしょうか。
ミイダスでコンピテンシー診断(特性診断)する
※登録後に無料で診断できます。


